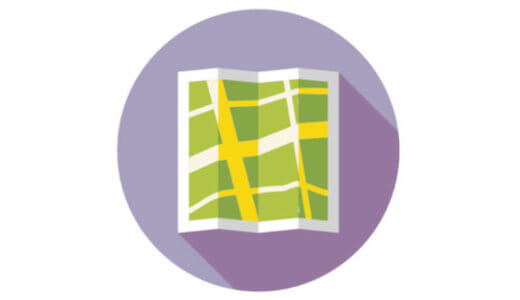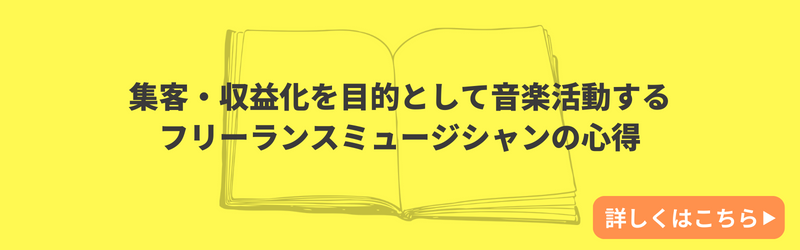こちらでは、コードの中の最低音(ベース音)を指定する「分数コード(オンコード、スラッシュコード)」の概念やその使い方について詳しく解説していきます。
あわせて、記事最後には動画による解説も行います。
目次
分数コード(オンコード、スラッシュコード)の概要
「分数コード(オンコード、スラッシュコード)」とは、「〇/〇」や「〇on〇」のように表記されるコードのことを意味する音楽用語です。
この表記は
分数コードの例
例えば「C」というコードの場合、そのベース音はコードのアルファベットとして表記されている「C」=「ド」の音となります。
- 構成音:「ド、ミ、ソ」
- ベース音:「ド」
これを
- 「C/E」
- 「ConE」
のようにした場合、これらは
- 構成音:「ド、ミ、ソ」
- ベース音:「ミ」
このように、通常分数コードでは「〇/〇」「〇on〇」の
- 左側(分数表記でいう分子側)がコード
- 右側(分母側)がベース音
を表します。
※これ以降は、「〇on〇」の表記を活用して解説を進めていきます。
分数コードの種類
分数コードは、構成音の状態をもとに以下のとおり大きく二つの種類に分けることができます。
1. 転回形の分数コード
まずひとつめが「転回形(てんかいけい)」として解釈できる分数コードで、これは既にご紹介した「ConE」のようなコードを指すものです。
この「ConE」のベース音は上記で解説したとおり「E(ミ)」となりますが、この音は本来のコード「C」の構成音「ド、ミ、ソ」に含まれるものです。
つまり、「ConE」というコードは
だということがここからわかります。
ここでの
- 「ConE」
- 「C」
の双方は同じ構成音によって成り立つため、そこからは根本的に同じ響きが生まれます。
つまり、転回形の分数コードは本来のコード(上記例における「C」)の響きが維持される、という特徴を持つものだといえます。
いろいろな転回形の分数コード
上記の概念をもとに、例えば「C」というコードからは他にも
「ConG」(「ドミソ」のコードでベース音のみを「G(ソ)」にする)
などの分数コードを作ることもできます。
また、コード譜などでよく見かける
- GonB(「ソ・シ・レ」+ベース「シ」)
- DonF#(「レ・ファ#・ラ」+ベース「ファ#」)
- AonC#(「ラ・ド#・ミ」+ベース「ド#」)
- EonG#(「ミ・ソ#・シ」+ベース「ソ#」)
- FonA(「ファ・ラ・ド」+ベース「ラ」)
- B♭onD(「シ♭・レ・ファ」+ベース「レ」)
- EmonB(「ミ・ソ・シ」+ベース「シ」)
などはすべて転回形のコードとして解釈できます。
2. 転回形にならない分数コード
分数コードの種類のうち、もうひとつは「転回形にならないもの」です。
例えば「GonC」というコードは
「G(ソシレ)」+ベース音「C(ド)」
という構成音によって成り立ちますが、ここでの「ド」の音は本来のコード「G」に含まれないものです。
つまりこれは「GonC」が転回形の分数コードではないことを意味しており、そのような理由から
- 「GonC」
- 「G」
のそれぞれは異なる響きを生みます。
このような「GonC」のサウンドは、分数コードならではのものだといえるでしょう。
コード構成音から分数コードを解釈する
分数コードを理論的に把握するにあたり、まず本来のコード(分子側にあるコード)の構成音を明らかにし、「on〇」で指定された音がそこに含まれるかを確認することで
転回形の分数コードか・そうではないものか
という点を明確にすることができます。
これはつまり
その分数コードによってサウンドに特徴的な響きが生まれているか
を測る目安となり、それが分数コードの効果や使用目的を考える助けとなります。
全体の構成音から他のコードを連想する
そもそも、分数コードの多くはなんらかのコードと同じ構成音を持ちます。
例えば「AmonG」という分数コードは
「Am(ラドミ)」+ベース音「G(ソ)」
という構成音によって成り立つため、上記でいう「転回形ではない分数コード」にあたるものとして解釈できます。
そのうえで、これと同じ「ラ、ド、ミ、ソ」とう構成音によって成り立つ「Am7」というコードが存在しているため、ここから
「AmonG」は「Am7」の転回形である
という解釈も同じようにできてしまいます。
▼関連ページ
 セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について
セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について
ここでの例のように、分数コードの多くはセブンスやテンションを含むコードと同じ構成音になることが多いです。
この例のように、構成音全体を他のコードに置き換えることも分数コードを理論的に把握するうえで効果的だといえます。
分数コード(オンコード、スラッシュコード)の代表的な活用例
実際の曲中において、分数コードが活用される場面は大きくいくつかに分けることができます。
以下に、その代表的なものを挙げます。
1. ベースラインをスムーズにつなぐための分数コード
最も一般的なのは、「ベースラインをスムーズにつなぐ」という目的で活用される分数コードです。
例えば、
C→G→Am(キー=C)
というコード進行があった場合、ここでのベース音は
ド(C)→ソ(G)→ラ(A)
とう流れとなり、そのキーのスケール「ドレミファソラシ」を前提とすると若干いびつなラインになっていることがわかります。
そこで、「G」を既にご紹介した転回形の分数コード「GonB」にすることで、ベースラインが
ド(C)→シ(B)→ラ(A)
となり、よりスムーズな流れを生み出すことができます。
他にも、例えば
- G → DonF#→ Em
- D → AonC#→ Bm
- A → EonG#→ F#m
- D → BonD#→ Em
などにおけるそれぞれの分数コードは、すべて同じような観点によって活用されているものです。
2. ベースラインを動かさないための分数コード
もうひとつは「ベースラインを動かさない」ということを目的として活用される分数コードです。
例えば
C→F→G
というコード進行からは
ド(C)→ファ(F)→ソ(G)
という流れによってベースが次々と切り替わっていく響きが感じられます。
そのうえで、あえてベースを動かさず、どっしりとした雰囲気を保ちながらコードの色合いだけをわずかに変化させたいような場合には、
C→FonC→GonC
のように、二つ目以降のコードに「onC」を付加し、ベース音を保持するようなアプローチが取られます。
この例における「FonC」「GonC」のそれぞれは
- FonC(「ファ・ラ・ド」+ベース「ド」)※転回形
- GonC(「ソ・シ・レ」+ベース「ド」)※転回形ではない
となり、既に例としてご紹介したとおり「GonC」の部分で特徴的な響きが生まれますが、このように偶発的な響きを意図してベース音が保持されることもあります。
3. ドミナントセブンスに近い役割を果たす「IIm7onV」の分数コード
分数コードの代表的な活用例として最後のひとつに挙げられるのが、「IIm7onV」の形です。
これは、ダイアトニックコード内において「サブドミナント」の響きを持つ「IIm7」に、ドミナント「V」のベース音が組み合わされた分数コードです。
▼関連ページ
 ダイアトニックコードとスリーコード(概要や成り立ち、コードの役割などについて)
ダイアトニックコードとスリーコード(概要や成り立ち、コードの役割などについて)
このコードは、
表面的なコードのサウンドは「サブドミナント」でありながらコードの性質は「ドミナント」である
という点に響きの面白さがあり、そのような意味から「優しい響きを持ったドミナント」というような観点でも活用されています。
以下は、一般的な構成とそのうちの「V7」を「IIm7onV」に置き換えた構成(キー=Cメジャー)の比較例です。
(I→VIm→V7→I)
(I→VIm→IIm7onV→I)
その他の例
これら以外にも、例えばキーCメジャーにおいて
F→GonF→Em→Am
のような分数コードの活用例も頻繁に見かけられますが、ここでは元の
ファ(F)→ソ(G)→ミ(E)…
というベースラインが分数コードによって
ファ(F)→ファ(F)→ミ(E)…
とアレンジされており、ここでの「GonF」は上記例における「ベースラインをスムーズにつなぐ」という目的によって活用された分数コードだと解釈できます。
また、別の見方をすると
F→GonF
という構成ではベース音の「F(ファ)」が保持されており、これは「ベース音を動かさない」という目的によるものともいえます。
つまり、これは上記で解説した二つの目的を兼ねるような分数コードの活用例だと解釈できますが、このように複数の見方によって読み解くことができる構成も頻繁に目にすることができます。
動画で解説
「文章ではよくわからない」という方のために、以下の動画でも分数コード(オンコード、スラッシュコード)について、実演を交え解説しています。
まとめ
以下は、分数コードについてのまとめです。
- 「分数コード(オンコード、スラッシュコード)」とは「ベース音のみを他の音に差し替えたコード」
- その種類は「転回形になるもの/そうではないもの」の大きく二種類に分けられる
- ベースをスムーズにつないだり、ベースを保持したり、「IIm7onV」の形にするなどの目的で活用されることが多い
上記でも述べたとおり、分数コードはある意味で編曲的な観点によるコードともいえます。
効果的に活用することで曲全体の響きをより豊かにすることができるため、是非作曲に取り入れてみて下さい。


 著者:
著者: