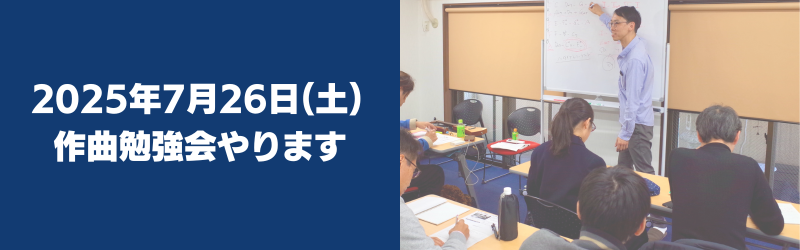こちらでは、ポップス・ロックの作曲において欠かせない「ダイアトニックコード」に関して、
- ダイアトニックコードとはどのようなものなのか
- ダイアトニックコードに含まれる「スリーコード」の内容
などを中心に解説していきます。
▼関連ページ
目次
ダイアトニックコードの概要
「ダイアトニックコード」=「ダイアトニックスケール」のコード
「ダイアトニックコード」とは
「ダイアトニックスケール」をコードに置き換えたもの
であり、ここで述べている「ダイアトニックスケール」とは簡単にいえば「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」のように、
「(法則に沿って)1オクターブを七つの音階に分けた状態」
を指す言葉です。
そもそも、音楽はピアノの鍵盤(以下図)を見るとわかる通り「7個の白鍵」と「5個の黒鍵」=「12個の音」のみによって成り立つものです。
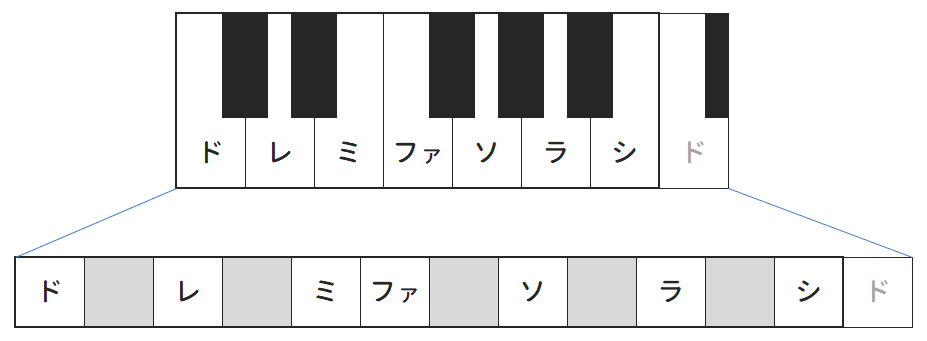
12音それぞれは実際のところ上記図のように等間隔で並んでおり、多くの人にとって馴染み深い「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」は
12音から特定の規則(並び方、選び方)に沿って選ばれた7音
だといえます。
既にご紹介した「ダイアトニックスケール」はその総称で、これは別名で
- メジャースケール
- マイナースケール
などとも呼ばれるものです。
▼「メジャースケール」「マイナースケール」解説ページ
上記で述べた通り「ダイアトニックコード」はこれをコードに置き換えたものであり、そのほとんどは
- メジャーダイアトニックコード(メジャースケールをもとにしたもの)
- マイナーダイアトニックコード(マイナースケールをもとにしたもの)
を指します。
こちらでは、中でも特に有名な「メジャーダイアトニックコード」を前提として解説を進めていきます。
スケールをもとに作られるコードのグループ
「ダイアトニックコード(メジャーダイアトニックコード)」はメジャースケールに含まれるそれぞれの音を起点として作られます。
これは、例えば「キー=Cメジャーのダイアトニックコード」というとき、
Cメジャースケール=「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」
の7音それぞれを最低音とした七つのコードを作り上げること、を意味します。
スケール内で1音飛ばしで積み上げる
上記の7音それぞれは「根音=ルート」と呼ばれ、そこから例えば、
- 「ド・ミ・ソ」
- 「レ・ファ・ラ」…
というように、低い音からスケールに沿って1音飛ばしで音を重ねて作られます。
以下は「Cメジャーダイアトニックコード」の構造を表にしたものです。

上記表にある通り、「Cメジャーダイアトニックコード」として
C,Dm,Em,F,G,Am,Bm-5
の7つのコードを割り出すことができます。
以下は、同じ手順によって全12キー分のダイアトニックコードを割り出した表です。

コードに「m」が付いたり「-5」が付いたりする理由
上記の「Cメジャーダイアトニック」のコードを見ると、
- 「C」「F」「G」=メジャーコード
- 「Dm」「Em」「Am」=マイナーコード
- 「Bm-5」=マイナーフラットファイブコード
というように、コードの種類がそれぞれで微妙に異なっていることがわかります。
これは、ダイアトニックコードの元となる「メジャースケール」の構造によるものです。
以下は、それをわかりやすくするために「C(ド・ミ・ソ)」と「Dm(レ・ファ・ラ)」の構成音の関係を表した図です。

上記図を見るとわかる通り、「C」「Dm」のそれぞれはCメジャースケールに沿って
- 「ド・ミ・ソ」
- 「レ・ファ・ラ」…
と音を重ねただけのコードですが、その元になるメジャースケールがいびつな構造になっているため、ここでの例における「『ルート』から『次の音』」にあたる
- 「ド」から「ミ」
- 「レ」から「ファ」
のそれぞれで長さに違いが生まれます。
これが、コードが「メジャーコード」になったり「マイナーコード」になったりする理由です。
▼関連ページ
コードの構造や度数の概念に関して詳しくは上記ページにて解説していますが、ここでは、
メジャースケールの構造がいびつであるため、「1音飛ばし」という同じルールに沿って音を重ねても起点となる音によってコードの構造に違いが生まれる
という点のみを理解して下さい。
「ダイアトニックコード」にはスケール内の音しか使われていない
改めて上記の表を見ると、この例の場合すべてのコードが「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の音だけによって成り立っていることがわかります。
スケールに沿って音を重ねているためこれは当然なのですが、言い換えればこれは
「メジャースケールから外れた音が無い」
ということを意味します。
そもそも、ポップス・ロックの楽曲は、「キー」という概念をもとにそのキーのメジャースケールの音を土台として成り立っており、ダイアトニックコードはそのメジャースケールをコードに置き換えたものです。
▼関連ページ
すなわち
「ダイアトニックコードはキーに準拠したコード進行を作るうえでの骨組みになる」
ということです。
当然のことながら、あるキーにおいて「そのキーのメジャースケールで歌われるメロディ」と「そのキーのダイアトニックコード(メジャーダイアトニックコード)によって作られたコード進行」は調和します。
作曲や音楽の成り立ちを考えるうえで、
- メロディ=メジャースケール
- コード進行=(メジャー)ダイアトニックコード
のそれぞれによって組み立てられるもの、と覚えておくと便利です。
「スリーコード」について
代表的な三つのコード
ダイアトニックコードの中でも、
- 「一番目(I)」
- 「五番目(V)」
- 「四番目(IV)」
にあたるコードは特に主要なコードとして「主要三和音=スリーコード」という呼び名で扱われます。
三つの役割(機能)
スリーコード内の三つのコードそれぞれには、その響きをもとにした役割(機能)があります。
以下はその一覧です。
- 「I(C)」= 安定(トニック) 「落ち着く響き」
- 「V(G)」= 不安定(ドミナント) 「落ち着かない響き」
- 「IV(F)」= 少し不安定(サブドミナントD) 「少し落ち着かない響き」
これら三つの響きはコード進行に表情を与える役割を持ち、曲の中でそれらを活用しながら、文章でいう「起承転結」のようにコード進行のストーリーが演出されます。
この「コードの機能を活用したストーリー」は、安定(トニック)に回帰することを前提として「カデンツ」という名称によって以下の3パターン種類に整理されています。
※「T」=トニック(安定)、「D」=ドミナント(不安定)、「SD」=サブドミナント(一時不安)
- 「T→D→T」(C→G→C)
- 「T→SD→D→T」(C→F→G→C)
- 「T→SD→T」(C→F→C)
ポップス・ロックの作曲では、上記「カデンツ」がコード進行の「型」のような存在となります。
▼関連ページ
まとめ
以下は解説のまとめです。
- 「ダイアトニックコード」とは「スケールをもとに作られるコードのグループ」
- スケールの構造がいびつであるためダイアトニックコードの7つのコードもそれぞれで構造が微妙に異なる
- ダイアトニックコードにおける「I」「V」「IV」は主要な三つのコードとして「スリーコード」と呼ばれる
- コードが持つ響き(機能)を活用して、コード進行のストーリーを演出できる
既に述べた通り、ダイアトニックコードはコード進行を作るうえでの基本となるものです。
上記をもとに、実際にコードを鳴らしながらそれぞれの響きを体感してみて下さい。
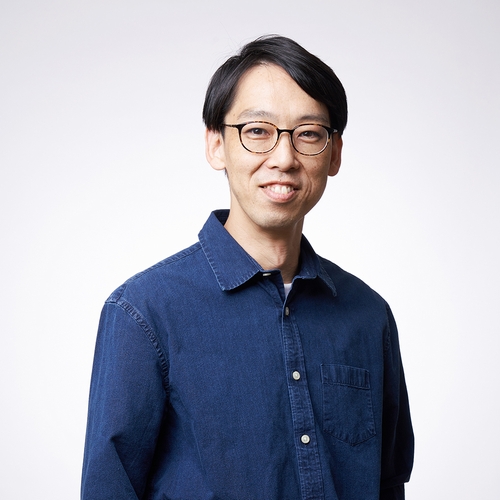
ポピュラー系のコード進行において、ダイアトニックコードは主役のような存在になります。
音楽理論について詳しく知る
 音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る
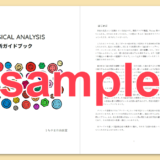 作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ
作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

 著者:
著者: