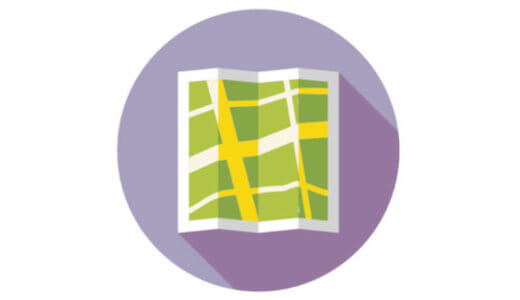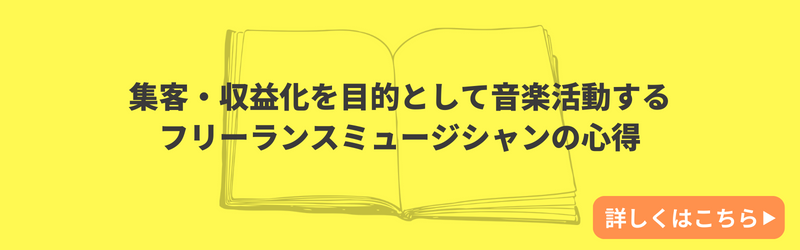こちらではコード進行の技法のひとつとして知られている「クリシェ」について、その内容と使用例を解説していきます。
あわせて、記事最後では動画による解説も行います。
目次
クリシェの概要
「クリシェ」とは、コードの中のあるひとつの音を順番に下げたり上げたりしてコードそのものを変化させながら繰り返してつなげていくコード進行の技法を指す音楽用語です。
詳しくは後述しますが、例えば
C→Caug→C6…
のようなコード進行があった場合、ここに含まれるコードそれぞれは
- C=ド、ミ、ソ
- Caug=ド、ミ、ソ#
- C6=ド、ミ、ソ、ラ
という構成音を持ち、コード進行全体を通して「C」という響きは保たれながらも、赤字で示しているように出発点となる「C」に含まれる「ソ」の音が
「ソ」→「ソ#」→「ラ」
と変化します。
これはクリシェの典型的な例で、上記で挙げた「C→Caug→C6…」のような流れは
- 「C」というルート音や構成音の大部分が保持される
- 構成音の一部が微妙に変化しサウンドに揺らぎが生まれる
という特徴を持ちます。
そのため、クリシェの技法はコード進行の安定感を保ちながらも微妙に響きを変化させサウンドに表情をつけたい時などに重宝します。
クリシェの使用例
コード進行が上記で述べたような構造を持つ場合、それらは基本的にすべてクリシェだと解釈できます。
そのうえで、実際のところポップス・ロック等においてクリシェが扱われるケースはいくつかに限られています。
これ以降では、その代表的なものをご紹介します。
1. 「I」の1度を順番に下げる
まずひとつ目の例は、コード構成音における「1度」の音を順番に下げていくようにつなげるやり方です。
そもそもコード(三和音)は、例えば「C」の場合
- ド=1度
- ミ=3度
- ソ=5度
の3音によって成り立ち、ここに記している「1度、3度、5度」の音は三和音の骨組みとなるものです。
▼関連ページ
 【コード(和音)とは?】 音楽で扱われている「コード」はどのように成り立っているか?を考える
【コード(和音)とは?】 音楽で扱われている「コード」はどのように成り立っているか?を考える
コードに関する詳しい解説は上記ページに譲りますが、このうちの「1度」を下げるようにラインを作るのがこちらのクリシェです。
こちらでご紹介するのはダイアトニックコードの1番目(I)のコードにおいてそれを活用するもので、以下はキー=Cメジャーにおける例です。
ここに含まれるコードそれぞれは
- C=ド、ミ、ソ
- CM7=ド、ミ、ソ、シ
- C7=ド、ミ、ソ、シ♭
- C6=ド、ミ、ソ、ラ
という構成音を持ち、ここでも赤字で示した通り、コードが進むに従って
「ド」→「シ」→「シ♭」→「ラ」
という音の変化が生まれます。
「1度」を「8度」と捉える
この例では、一番目のコードである「C(I)」を起点として、二番目のコードには
「C」に「長7度(「シ」の音)」を付加した「CM7(IM7)」
が使用されており、またそこから後には
- 「短7度(「シ♭」の音)」を付加した「C7(I7)」
- 「長6度(「ラ」の音)」を付加した「C6(I6)」
が続けられています。
ポイントとなるのは、一番目のコードにおける「1度」の音をオクターブ上の「8度」として解釈している点で、それによって
「8度→長7度→短7度→長6度」
という流れが作られています。
ノンダイアトニックコードの使用
また、ここでの「C7(I7)」は「シ♭」の音(キー=Cメジャーに含まれない音)を持つため、一般的に
ダイアトニックコードに無いコード(=ノンダイアトニックコード)
として解釈されます。
このように、違和感なくノンダイアトニックコードをコード進行の中に盛り込める点もクリシェの特徴のひとつといえます。
2. 「IIm」「VIm」の1度を順番に下げる
次にご紹介するのは、上記と同じやり方をダイアトニックコードの二番目および六番目のコード(IIm、VIm)に適用させるものです。
以下は、同じくキー=Cメジャーにおける「Dm(IIm)」「Am(VIm)」でそれを実施した例です。
「C(I)」の例と同様に、それぞれ
- 「Dm」における「レ」の音
- 「Am」における「ラ」の音
を起点として、クリシェによって
- 「レ」→「レ♭」→「ド」→「シ」
- 「ラ」→「ラ♭」→「ソ」→「ソ♭」
というラインが生まれます。
このように、1度の音を下げていくクリシェはマイナーコードにも活用することができます。
3. 「I」の5度を順番に上げる
次にご紹介するのは、ページ冒頭でもご紹介した通り、コード構成音である「1度、3度、5度」のうち、「5度」の音を順番に上げるようにしてつなげるクリシェです。
以下に、キー=Cメジャーにおける例を改めて示します。
既に解説した通り、このクリシェでは「C=ドミソ」のうちの「ソ(5度)」が変化し、
「ソ」→「ソ#」→「ラ」→「ラ#」
というクリシェラインが生まれます。
「5度」の変化
このクリシェでは、二番目のコードに
「C」の「5度」を「増5度(「ソ#」の音)」にした「Caug(Iaug)」
が使用され、またそこから後には
- 「長6度(「ラ」の音)」を付加した「C6(I6)」
- 「短7度(「シ♭」の音)」を付加した「C7(I7)」
が続けられています。
「1度」を下げるクリシェと似たような形で、これによって
「5度→増5度→長6度→短7度」
という度数の変化が生まれます。
※度数に関して、詳しくは以下ページにて解説しています。
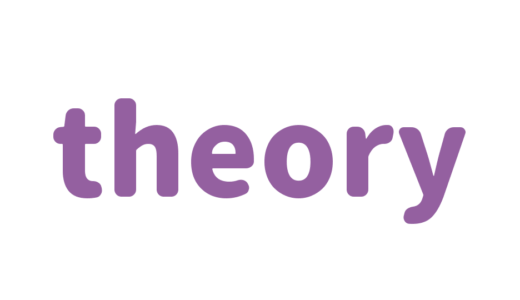 音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)
音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)
「1度」を下げるクリシェに比べてこちらの「5度」を上げるクリシェは使用される範囲が狭く、ここで例として挙げた通りダイアトニックコードの一番目のコードに使用されることがほとんどです。
また、このクリシェでは
- 「Caug(Iaug)」
- 「C7(I7)」
の二つがノンダイアトニックコードとなるため、より個性的な雰囲気が感じられるところも特徴のひとつだといえます。
クリシェの応用
ここまでに解説したクリシェの基本的な手法は、実際の楽曲の中では頻繁にアレンジされます。
以外にその代表的な例を挙げます。
1. クリシェラインをベースに置き換える
まずひとつ目は、クリシェラインをベースに置き換えるやり方です。
以下は、既にご紹介した「『VIm』の1度を下げるクリシェ」でそれを実施した例です。
↓
アレンジ:Am→AmM7onG#→Am7onG→Am6onF#
ここでは、既に述べた
「1度(8度)→長7度→短7度→長6度」
という音の変化がそのままベースラインに置き換えられています。
通常のクリシェがルートを保ちながら展開していくのに対し、このアレンジではベースラインが動くことによって「コードが展開している」という雰囲気が生まれ、半音で変化するクリシェラインをより際立たせることができます。
コード本体を変えずベースだけが動く例
また、上記をコード本体にクリシェを盛り込まずに実施すること(以下例)もできます。
この例では「Am」というコードが保持されたまま、ベースラインのみが半音で下がっています。
ここまでくるとクリシェの本来の意味からは若干遠のいてしまいますが、ベースアレンジのひとつの形としてこのようなパターンも想定することができます。
2. クリシェを次なるコードの足掛かりにする
もうひとつのアレンジ例が、クリシェによって生まれたクリシェラインを次なるコード展開の足がかりにするものです。
以下は「『I』の1度を下げるクリシェ」における例です。
↓
アレンジ:C→CM7→C7→F
ここではクリシェによってもともと想定できた「C6」を「F」に差し替えています。
そもそも、このクリシェでは
「ド」→「シ」→「シ♭」→「ラ」
というラインが作られていますが、「F」のコードには「C6」と同じく「ラ」の音が含まれているため、
- 「F」と「C6」を置き換えてもクリシェラインが保たれる
- 上記差し替えによって直前の「C7」から「C7→F」というドミナントモーションを作れる
という二つの理由によって「F」のコードを違和感なく盛り込むことができています。
▼関連ページ
 セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します
セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します
クリシェラインの先に他のコードを置くことによって、クリシェを単なるひとつのかたまりではなく、コード進行の流れのひとつとして機能させることができます。
動画で解説
「文章ではよくわからない!」という方のために、以下の動画でもクリシェについて実演を交え解説しています。
まとめ
以下はクリシェについてのまとめです。
- クリシェとはひとつのコードの中の音を順番に下げたり上げたりしてコードそのものを変化させていくコード進行の技法
- 主に「1度」を下げるクリシェと「5度」を上げるクリシェの2パターンが利用される
- クリシェは自由にアレンジして活用される
根本的にクリシェは「ひとつのコードを保つ」という発想が元になっているため、比較的簡単に利用することができます。
コード進行に表情を与えたいような場面で、是非クリシェを上手に活用してみて下さい。


 著者:
著者: