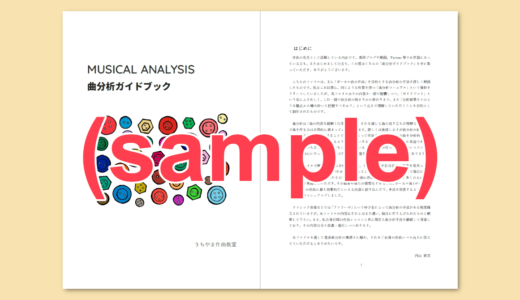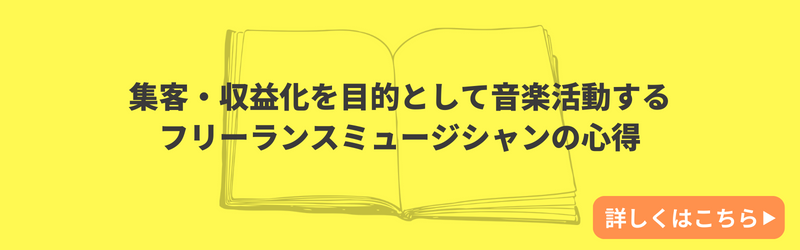私が普段作曲の先生として活動している中で、思いのほか多くいただくのが
という質問です。
確かに、「作曲」という言葉はどこか抽象的で範囲が曖昧なため、初心者の方がそのような疑問を抱えてしまうのも理解できます。
こちらのページでは、そんなみなさんに向けて「作曲」の範囲や、「どこまでやることが『作曲』なのか?」という点について考えていきます。
目次
「作曲」が持つ二つの意味
実際のところ「『作曲』がどこまで作ることを指すのか」という点については、人によってその見解が分かれます。
その上で、一般的な解釈は、
- 作曲=曲を演奏の情報も含めすべて考え仕上げること
- 作曲=メロディやコード進行など、大まかな曲の骨組みのみを作ること
というどちらかになることが多いです。
前者はクラシックなどにおける「作曲」や、最近主流になりつつあるDTMを使った音楽制作を指すものです。
また、後者は商業音楽として発展した「作曲」の姿です。
「作曲」と「編曲」の例
「作曲家」が曲のすべてを作り込むパターン
そもそも、歴史に名を残す偉大な作曲家は、曲を耳にできる状態まですべて作り込んだうえで「作曲家」として認識されています。
以下は、多くの人が知っているクラシックの楽曲「運命」です。
この曲の作曲家はご存知のどおり「ベートーヴェン」ですが、例えばこの動画にあるような「バイオリンはここでこんなフレーズを弾いて…」というような演奏の情報を含め、曲に関する全ては彼の手によって作り込まれています。
これは上記で挙げた「作曲の二つの解釈」のうち、前者(曲のすべてを作ること)に相当するもので、
という図式が簡単にイメージできるはずです。
「作曲」のあとに、別工程として曲を作り込むパターン
一方で、以下はビートルズの「While My Guitar Gently Weeps」という楽曲です。
この曲を作ったのはジョージ・ハリスンであるため、
となります。
そのうえで、本来この楽曲は以下のような音源としてリリースされています。
これは、前述のジョージが作った「ギター1本の弾き語りバージョン」を土台として、それをバンドサウンドにアレンジした状態です。
この演奏情報を作り上げたのはらはビートルズのメンバーやプロデューサーなどですが、本作を楽曲として成立させているのがこれらのサウンドやアレンジだとするなら、上記「ベートーヴェン」の例を元にして
となってもよさそうです。
しかし、一般的にはここでいう
は「編曲」として捉えられており、それらをもとにして「作曲者」「編曲者」は
- 作曲=ジョージ・ハリスン
- 編曲=ジョージ・ハリスン、ビートルズのメンバー、他数人
のように認識されています。
「作曲」が「編曲」になるときがある
上記を整理すると、状況によって「曲のすべてを作ること」を「作曲」というときもあれば、それを部分的に切り取って「編曲」という言葉で表現するときもある、ということです。
これが
をわかりづらくさせてしまっている原因だと考えられます。
結局のところ「作曲」はどこまで?
そのうで、結局のところポップス・ロックにおける「作曲」は、前述したジョージの「ギター1本の弾き語りバージョン」を作ることだとするのが一般的です。
そして、やはり「それをどう演奏するか」は「編曲」という名前によって捉えられます。
「作曲」で目指すもの
これをもとに、作曲に慣れないうちはまず
を作曲のゴールとして設定して下さい。
「メロディとコード進行と構成」(曲の骨組み)とは、つまり前述の「While My Guitar Gently Weeps」の「ギター1本弾き語りバージョン」と同じような状態です。
「編曲」でどのようにでもなる
実際のところ、その「メロディとコード進行と構成」がきちんと完成していれば、それを編曲によってどのようにでも聴かせることができます。
以下は、同じく「While My Guitar Gently Weeps」をアレンジしたさまざまなバージョンの例です。
これらの例のように、同じメロディ・コード進行・曲構成でもアレンジによってさまざまな曲調にすることができるのです。
ここから、楽曲を魅力的なものにするためには、根本的に「作曲」という工程において「メロディとコード進行=曲の骨組み」をしっかりと作り込んでおくことが大切だとわかります。
まとめ
ここまで、「『作曲』はどこまでを指すのか?」という点について考えてきました。
まとめると
- 「曲のすべてを作る」「曲の骨組みのみを作る」という二つの解釈ができる
- 状況によって「作曲」が「編曲」になることもある
- ポップス・ロックでは「メロディとコード進行と構成」を作ること「作曲」と捉えると作業を進めやすい
となります。
編曲には作曲とはまた違った観点が必要になるため、まずは上記「作曲」を通して曲作りの基本を学び、それらを「編曲」によってさまざまな曲調に仕上げていくことを目標としてみて下さい。


 著者:
著者: