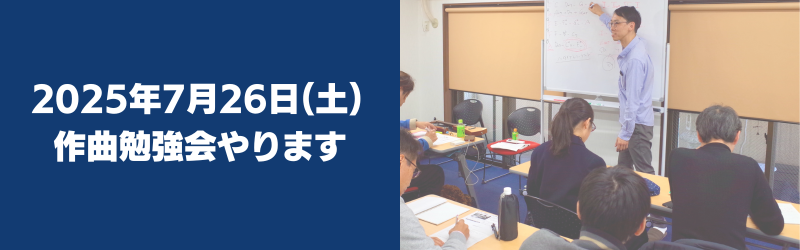ポップス・ロックの作曲や演奏では、「Aメロ」「Bメロ」「サビ」という用語を頻繁に活用します。
こちらのページではそれらの意味と、それを含めた「曲形式」の概念について解説していきます。
目次
「Aメロ」「Bメロ」「サビ」とは「まとまり」のこと
「Aメロ」「Bメロ」「サビ」とは、「楽曲の中で感じられるまとまり」を指す言葉で、厳密には「Aのまとまり」「Bのまとまり」「サビのまとまり」などと捉えることができます。
この「A」「B」という名称は慣例的なもので、それぞれのまとまりを区別するための、いわば箇条書きにおける行頭文字(「a,b,c…」や「一,二,三…」など)のようなものです。
ブロック(セクション)により場面転換を演出する
通常ポップス・ロックなどの曲は、展開に沿って雰囲気を変えながらリスナーにストーリーを感じさせますが、その際に映画や舞台における「場面」のような役割を担うのが「ブロック(セクション)」という概念です。
曲中のある部分に(メロディやコード・リズム・演奏などによって)統一感を持たせ、それを曲の冒頭から
「Aブロック」→「Bブロック」
のように切り替えていくことで場面転換=ストーリーを演出することができるようになるのです。
ブロックの例
以下は、上記の概念をわかりやすく把握するために、例として童謡「いぬのおまわりさん」におけるブロック(セクション)を整理したものです。
「まいごのまいごの…」
「おうちーをきいてもわからない…」
「いぬのー、おまわりさん…」
ここで挙げている三つのメロディは曲の展開に沿って順番に登場しますが、リスナーとしてこの曲を聴くときにはそれぞれの部分で少し雰囲気が変わることを体感できるはずです。
これが「ブロック」の概念で、その雰囲気の移り変わりが曲のストーリーを生み出します。
ブロックの感じ方は人それぞれ
実際のところ、ここで挙げている「まとまり」の感じ方は人それぞれで、例えば上記で整理した「Aメロ」と「Bメロ」を「ひとつのまとまり」として感じる人もいるはずです。
そのような意味から、「Aメロ」「Bメロ」という明確な区分けは作曲者のみがその答えを知っていることになります。
本来この「A」「B」という呼び名は楽譜における「リハーサルマーク」という概念が元となっており、演奏や録音の場面などでは関係者全員の認識を揃えるために、楽譜における表記によってそれぞれのまとまりが明確に区分けされます。
ブロックを意識して作曲することが大切
作曲をする際には、上記でご紹介した「Aメロ」「Bメロ」というようなブロックの概念を意識し、その転換やつながりをリスナーに対してきちんと提示することが大切です。
それにより、既に述べたような場面転換が明確になり、楽曲はドラマチックで聴きごたえのあるものに仕上がっていきます。
この
「ブロックをどのようにつなげてどう展開させるか」
という考え方は「曲の形式」などと呼ばれます。
曲形式について
これ以降は、ポップス・ロックでよく活用されている曲の形式についてご紹介していきます。
今回ご紹介するのは以下の二つです。
- 「Aメロ→Bメロ→サビ」
- 「Aメロ→Bメロ→Aメロ」
形式1:「Aメロ→Bメロ→サビ」
まず初めにご紹介するのが、三つのブロックが場面転換しながらつながっていく
「Aメロ→Bメロ→サビ」
の形です。
80年代以降のポップスでは頻繁に扱われており、シンプルな構成でありながらも三段階の展開によりストーリーを演出しやすいところがその特徴です。
そのような理由から、短い時間ではっきりとしたストーリーを演出することが求められるポップス・ロックなどの楽曲には適した曲形式であるといえます。
「A→B→サビ」のAメロ
「A→B→サビ」形式におけるAメロは曲の導入部分であるため、一般的に落ち着いた雰囲気を持ったものとして作り込まれます。
「リスナーが抵抗なく曲に入り込める」ということを目的としてメロディやコードなどが作り込まれるため、
- コードチェンジのタイミングが少ない
- メロディの起伏が少ない
- メロディの音域が低い
- リズム的なアクセントが少ない
などの特徴を含むことが多いです。
また、Aメロ以降の曲展開を期待させる為になんらかの「つかみ」を設けることもあり、その場合には少し特徴的なメロディ/コードなどが盛り込まれることもあります。
「A→B→サビ」のBメロ
「A→B→サビ」形式におけるBメロはAメロとサビをつなぐ中間のブロックとも言い換えることができます。
そのため、
- 導入部としてのAメロを雰囲気を上手く受け継ぐ(またはAメロから大きく場面転換する)
- サビへ向けて盛り上がっていく
などの性質が求められるます。
一般的にBメロは制約の少ないブロックである為、個性的な手法もよく活用されています。
この形式におけるBメロはサビの直前に位置するため、いずれの場合にも「サビより目立たない」という条件が重視されます。
「A→B→サビ」のサビ
「A→B→サビ」形式におけるサビは「曲の顔」ともいえるブロックで、作り手のセンスが大いに発揮され、「いかに印象付けるか」ということを考えられながら作り込まれます。
典型的なかたちはいくつかあるものの、型にとらわれず、自由な発想で構築されることブロックだといえます。
形式2:「Aメロ→Bメロ→Aメロ」
次にご紹介するのが、タイプの違った二つのブロックをつなぎ合わせた
「Aメロ→Bメロ→Aメロ」
の形式です。
「提示部」と「展開部」を持った形式で、70年代のフォークソングや洋楽などで頻繁に見かることができます。
「A→B→A」のAメロ
「A→B→A」の形式は前述の「A→B→サビ」とは違って段階的に盛り上がる曲構成になっていないため、多くの場合このAメロが「曲の顔」になることが多いです。
そこから、この部分を
曲の始まりで一番印象に残るブロック=サビ
とも捉えることができます。
親しみやすいメロディやインパクトのある構成など、曲を印象付けるための配慮が必要となります。
「A→B→A」のBメロ
「A→B→A」の形式におけるBメロは「ブリッジ」とも呼ばれ、二つのAメロの中間で違った展開を聴かせる働きを持ちます。
その後にサビを持たないため、「A→B→サビ」形式におけるBメロに比べて単体で盛り上がる傾向が強く、Aメロとは違った魅力が求められます。
初期のビートルズはこの部分を8小節にして「ミドルエイト」などと呼んでいました。
「A→B→A」のAメロ(Bメロ後)
1回目のAメロと全く同じ構成とすることも多く、またあえて2回目のAメロを少し変化させるやり方もよく見かけられます。
まとめ
ここまで「Aメロ」「Bメロ」「サビ」という用語の意味と曲の形式についてご紹介してきました。
こちらでご紹介した二つ曲形式にも、実際の曲ではいろいろな発想によってブロックが繋げられ、さまざまな方法で場面転換が演出されています。
既存の曲を「Aメロ」「Bメロ」というブロックや「曲形式」という観点から分析して、そこでどのようなことが行われているかを把握するとその理解が深まるはずです。
是非作曲の参考にしてみて下さい。

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る
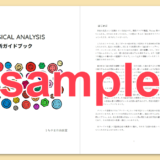 作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ
作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

 著者:
著者: