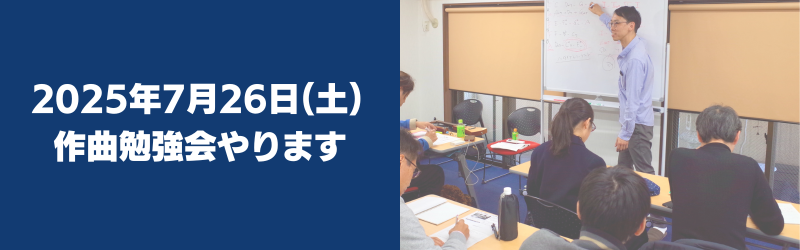こちらでは、コード進行の技法のひとつである「裏コード(うらこーど)」について詳しく解説していきます。
あわせて、記事最後では動画による解説も行います。
目次
「裏コード」の概要
「裏コード」とは、ダイアトニックコードを前提とした場合の「♭II7」のコードのことを指す音楽用語です。
これは、例えば「キー=Cメジャー」における「D♭7」(または「C#7」)のコードにあたるものです。
ドミナントセブンス(V7)に近い響きを持つ
この「♭II7」はドミナントセブンス(=V7)に近い構成音を持っており、似たような響きを生むことから「V7」からの置き換えのコードとして活用されます。
以下は、その例として「キー=Cメジャー」における「V7(ドミナントセブンス)」と「♭II7(裏コード)」の構成音を比較したものです。
- G7(V7)=ソ・シ・レ・ファ
- D♭7(♭II7)=レ♭・ファ・ラ♭・シ
上記例の「G7」における「シ~ファ」の音程は「増4度」と呼ばれるもので、数ある音程の中でも特に不安定な響きを持ち、それがドミナントセブンスの不安定なサウンドを生み出します。
上記に赤字で示した通り、「D♭7(♭II7)」の構成音には同じくその「シ~ファ」の組み合わせが含まれており、これは
「D♭7」は「G7」と同じように不安定な響きを持つ
ということを意味します。
「♭II7」が「V7」からの置き換えのコードとして活用されるのは、このような理由からです。
ドミナントセブンス(V7)は独特な響きを持っているため、とても重要なコードでありながらあまりにそれを多用するとありきたりな印象を与えてしまうことにもなります。
そのうえで、この裏コード(=♭II7)はドミナントセブンスのありきたりな響きアレンジする意味で、ジャズやR&Bなどの都会的なサウンドを持つ楽曲で度々利用されます。
裏コードの割り出し方
裏コードは「♭II7」=「♭II」をルート音とする「〇7」のコードであるため、
「♭II」は「I」の半音上
という考え方を用いてより直接的にそれを割り出すことができます。
つまり、
- 「V7→I」というコードの流れを想定する(例:「G7→C」)
- 上記のうち「I」の半音上のルートを持つ「〇7」が裏コード(例:「C」の半音上「D♭」をルートとする「D♭7」が裏コード)
という流れによって簡単に裏コードを導ける、ということです。
この概念によって、もっと直接的に、例えば「『F』の裏コードは?→『F#7』」というように、あるひとつのコードに対して即座に裏コードを導くこともできます。
「裏コード」の使用例
ドミナントセブンス(V7)からの単なる置き換え
上記で述べた通り、通常のコード進行の中で裏コードは「V7」の代わりとして活用されます。
以下は、トニック「I」の直前にドミナントセブンスコード「V7」を配置した構成と、それを「♭II7」に置き換えた構成の比較例(キー=Cメジャー)です。
(I→IV→V7→I)
(I→IV→♭II7→I)
上記を見るとわかる通り、ドミナントセブンスが裏コードに置き換わったことによりトニック「C」に向かうベースラインが
「レ♭(D♭)→ド(C)」
という半音階の流れになっています。
ドミナントセブンスと同じ役割を持ちながらも、このような半音進行の構成をつくることができる、というところに裏コードの面白さがあります。
サブドミナントからの流れを作る
上記コード進行をもとに、その中の「IV」をさらにダイアトニックコード内の代理コードである「IIm」に置き換えたものが以下の構成です。
(I→IIm→♭II7→I)
この例では、サブドミナントが「Dm(IIm)」に置き換えられたことで、サブドミナントからトニックにかけてのベースラインが、
「レ(D)→レ♭(D♭)→ド(C)」
とすべて半音進行となっています。
このように、「サブドミナント→ドミナント→トニック」という機能的なつながりを維持したまま半音階の構成を作り出すことができるところも裏コードの特徴のひとつだといえます。
セカンダリードミナントコードの裏コード化
既に述べた通り裏コードは「V7→I」を元とする概念であるため、同じ概念を用いた「セカンダリードミナントコード」にも同じように適用することができます。
▼関連ページ
 セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します
セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します
以下は、セカンダリードミナントコード「III7」を使用した構成と、それを裏コードによって置き換えた構成の比較例(キー=Cメジャー)です。
(IIm7→III7→VIm)
(IIm7→♭VII7→VIm)
この例では、セカンダリードミナントコードの「E7(III7)」がその裏コードである「B♭7(♭VII7)」に置き換えられていますが、この場合でも、前述した「裏コードの割り出し方」が活用できます。
すなわち、「E7→Am」という構成をドミナントモーション「V7→Im」の形として捉え、
「Am(Im)」の半音上の音をルートとした「B♭7(♭II7)」
を裏コードとして即座に導くことができる、ということです。
「Am(VIm)」に対するドミナントモーションの形は維持されたまま、裏コードによって部分的に耳慣れない響きが挿入されることでその部分がアクセントとなり、コード進行がより特徴的なものに感じられます。
動画で解説
「文章ではよくわからない」という方のために、以下の動画でも裏コードについて解説しています。
まとめ
以下は「裏コード」の解説まとめです。
- 「♭II7」を「V7」の置き換えとして活用できる
- 裏コードは「『I』の半音上の音をルートとした『〇7』」と覚える
- 裏コードはスムーズなベースラインを作るためにも活用される
裏コードはドミナントセブンス「V7」を使った構成に比べて扱いにくそうな印象を受けますが、まずは曲中にある「V7」を気軽に「♭II7」に変換していく感覚で使用することで、コードの持つ響きや使い勝手を体感できるはずです。

音楽理論について詳しく知る
 音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る
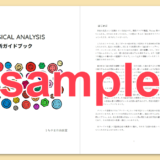 作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ
作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

 著者:
著者: