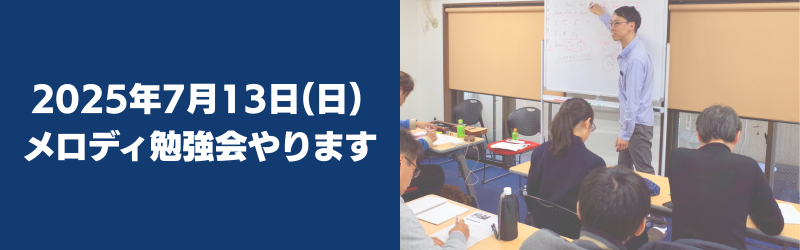こちらのページでは、ポップス・ロックなどでよく活用されている「6451進行」と呼ばれるコード進行の詳細と、それを使った曲の例などをご紹介していきます。
目次
「6451進行」の概要
今回テーマとしている「6451進行」とは、ダイアトニックコードにおける「六番目」「四番目」「五番目」「一番目」のコードを、
六番目→四番目→五番目→一番目
というように順番に使って展開させていくコード進行のことを指す言葉です。
▼関連ページ  ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて
ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて
以下にその例として、「Cメジャーダイアトニックコード」の7つのコードと、それらを活用した「6451進行」を示します。
(I,IIm,IIIm,IV,V,VIm,VIIm-5)
各キーのダイアトニックコードを明らかにし、「6→4→5→1」とコードを順番につなぐだけで簡単にこの進行を組み立てることができます。
この「6451」の形は音楽プロデューサーの小室哲哉さんが愛用していることから、「小室進行」という名前でも呼ばれることがあります。
親しみやすさの考察(1)マイナーがメジャーに変化する
前述した「Cメジャーダイアトニックコード」における例を見るとわかる通り、「6451進行」は
マイナーコードで始まりメジャーコードで終わる
という形となっています。
そこには、マイナーコードならではの暗く切ない響きがメジャーコードの持つ明るく前向きな響きに変化する面白さがあり、その短い構成の中からストーリーが感じられます。
この点が、「6451進行」を魅力的なコードの展開だと感じる一番の理由として挙げられます。
親しみやすさの考察(2)安定で始まり、安定で終わる
また、このコード進行で扱われている「VIm」および「I」のコードは安定した響きを持っており、リスナーに、
- 落ち着いている
- 展開が始まる/終わる
などの印象を与えます。
「6451進行」が「VIm」で始まり「I」で終わることから、これを
「『安定』で始まり『安定』で終わるコード進行」
とも言い換えることができます。
この点も、「6451進行」がコード進行として説得力のあるものに感じられる理由のひとつといえそうです。
親しみやすさの考察(3)スリーコードの超王道な流れを含む
「6451進行」に含まれる
「IV→V→I」
の流れは、コード進行の型としても知られている「カデンツ」の一部に相当するものです。
▼関連ページ  カデンツ(終止形)の詳細とポップス・ロック作曲への応用
カデンツ(終止形)の詳細とポップス・ロック作曲への応用
「カデンツ」について詳しくは上記ページで解説していますが、それらは既にご紹介した「安定(=トニック)」を含む以下三種の機能を組み合わせた「コード進行の最小単位」のようなものです。
- 安定(トニック)
- 不安定(ドミナント)
- 少し不安定(サブドミナント)
コードが持つ響きの分類はこれら三種のみで、中でもダイアトニックコードにおける「一番目(I)」「五番目(V)」「四番目(IV)」は、それぞれに
- 一番目(I)=トニック
- 五番目(V)=ドミナント
- 四番目(IV)=サブドミナント
という役割を持っており、上記で挙げた三種の分類を象徴する存在であることから「主要三和音(スリーコード)」などと呼ばれます。
「6451進行」における「IV→V→I」がまさにそのスリーコードをつなげたもので、三種の響きをもっともシンプルにつなげた流れを含んでいる、といえます。
これも、「6451進行」が親しみやすく説得力のあるコード進行だと感じる理由の一つとして挙げられます。
各キーにおける「6451進行」
既に述べた通り、各キーのダイアトニックコードと、そこでの「六番目」「四番目」「五番目」「一番目」のコードをつなげるだけで「6451進行」を簡単に作り上げることができます。
以下は、代表的ないくつかのキーにおける「6451進行」を示したものです。
セブンスコードによるアレンジ
ダイアトニックコードには、一般的な「三和音」によるもの以外にも「セブンスコード(四和音)」によるものが存在しています。
▼関連ページ  セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について
セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について
これらを活用すれば、「6451進行」をセブンスコードとしても表現することができます。
以下は、前述した「Cメジャーダイアトニックコード」による「6451進行」をセブンスコードで表したものです。
実際に音を聴いてみると、三和音の状態よりも響きが多彩になり、都会的な雰囲気が高まっていることがわかります。
このように、「6451進行」の親しみやすさを残しながら、セブンスコードによってそれをより聴きごたえのあるものにアレンジすることも、作曲をするうえでのひとつのヒントとなるはずです。
「6451進行」が活用された曲の例
以下に、「6451進行」が活用された曲の例を挙げます。
「Get Wild(TM NETWORK)」
「6451進行」が「小室進行」という名前で呼ばれるきっかけにもなったのがこの楽曲です。
イントロで繰り返されているコードの流れは、
で、これは「キー=Bメジャー」における「6→4→5→1」の形に相当するものです。
「6451進行」の響きを最も直接的に体感することができるはずです。
「survival dAnce(TRF)」
こちらも小室哲哉さんが手掛けたヒット曲で、曲冒頭における「no no cry more~」という部分から
というコードが扱われており、これは「キー=E♭メジャー」における「6451進行」に相当するものです。
この楽曲も、「小室進行」を語るとき頻繁に例として挙げられます。
「フライングゲット(AKB48)」
こちらの楽曲でも、上記「survival dAnce」と同じく
というコード進行がサビの冒頭で扱われています。
本作はロックなサウンドにアレンジされていますが、このような曲調にも「6451進行」は程良く馴染みます。
「馬と鹿(米津玄師)」
この楽曲の冒頭のコード進行も
の形で、これも「6451進行」です。
曲の導入部分から感じられる少し切ない雰囲気がこのコード進行によって生み出されたものだということがわかり、興味深いです。
「愛唄(GReeeeN)」
本作のサビで扱われているコード進行は
という構成で、これは「キー=A♭メジャー」における「6→4→5→1」の流れです。
既に述べた通り、「6451進行」からは「マイナー→メジャー」という響きの変化が感じられますが、本作のサビはそれを前面に押し出すように組み立てられています。
前述した「馬と鹿」と同じく、このようなミディアムテンポの楽曲にも「6451進行」は馴染みます。
補足
以下のページでは、今回のテーマである「6451」と似たような形で、コード進行を数字によって型にしたいくつかのパターンについてご紹介しています。
 コード進行を数字(度数)で表す利点・代表的な数字パターンの解説 キー別のコード進行を効率良く覚える/扱うための概念
コード進行を数字(度数)で表す利点・代表的な数字パターンの解説 キー別のコード進行を効率良く覚える/扱うための概念
まとめ
記事後半では、特に「6451進行」を象徴的に扱っている楽曲のみに絞りご紹介しましたが、これら以外にもさまざまな楽曲でこのようなコードの流れは多用されています。
お伝えした通り、このコード進行は親しみやすい響きを持ったものでありながら比較的簡単に扱うことができるため、作曲に導入することで是非その使い勝手を体感してほしいです。
また、既存の楽曲ではこの「6451進行」を崩したような構成も多く見かけられるため、分析を通してそれらも含めた手法を探ってみて下さい。
▼関連ページ  コード進行分析の方法 アナライズの手順とコツ・注意点などの解説(キー判別、理論的解釈など)
コード進行分析の方法 アナライズの手順とコツ・注意点などの解説(キー判別、理論的解釈など)

音楽理論について詳しく知る
 音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る
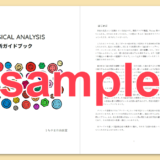 作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ
作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

 著者:
著者: