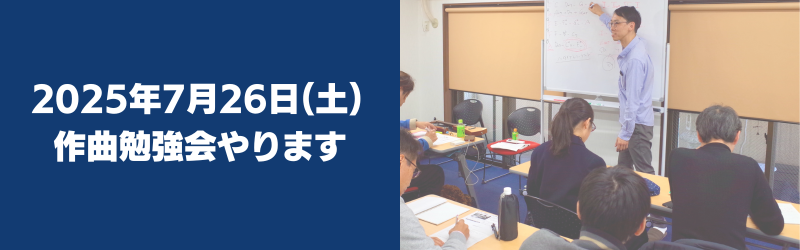こちらのページでは、「コードの動かし方」の手法のひとつとされる「強進行(きょうしんこう)=通称『4度進行』」について解説していきます。
あわせて「強進行」を活用したコード進行のアイディアと、記事最後には動画での解説も行います。
強進行の概要
心地良い音の動き
「強進行」とは「強い進行を感じさせるコードの動き」を意味する音楽用語です。
より簡単にいえば「聴いていて心地良いコードの動き」のことです。
音楽の中に強進行の構成があることで、リスナーはそこから「聴きやすさ」や「一貫性」のようなものを感じることができます。
そのような意味から、強進行はリスナーを納得させて感動させるために欠かせない概念ともいえるでしょう。
音の完全4度上行
強進行にはいくつかの種類がありますが、ポップス・ロックにおいては主に
完全4度上行(または完全5度下行)のルート音の動き
を指してこの言葉が使われます。
ここから、このような音の動きは通称として「4度進行」とも呼ばれています。
下記は完全4度上(または完全5度下)となる音の動きの例です。
- G → C
- E → A
- F → B♭ …など
コード進行において、ルート音(ベース音)が完全4度上行(または完全5度下行)することで「強進行」と解釈されます。
一般的には、ルート音がそのような関係になってさえいれば、コードの「メジャー・マイナー」や「セブンス」などを問わず、すべてが強進行と解釈されます。
下記は「強進行」とされるコード進行の例です。
- Gm → Cm
- F7 → B♭7
- C#m7-5 → F#7 …など
ダイアトニックコード内での「V → I」(「キー=C」における「G → C」)は完全4度上行の構成であるため、上記を踏まえると
ドミナントモーション(V7 → I)は強進行を利用した手法
として捉えることができます。
※ドミナントモーションの詳細については下記をご参照ください。
 ドミナントセブンスとドミナントモーションについて|コード進行を操る重要な働き
ドミナントセブンスとドミナントモーションについて|コード進行を操る重要な働き
ダイアトニックコード内の進行で「強進行」を活用するアイディア:キー=C
上記で述べた通りルート音のつながりが「強進行」になるようコード進行を組み立てていくと、それぞれのコードがスムーズにつながっていきます。
以下に、「キー=Cメジャー」を前提として、ダイアトニックコード内で強進行を作るアイディアを挙げます。
1.ドミナントモーション型
- G → C(V → I)
既にお伝えした通り、「V」から「I」への進行は完全4度上行となります。
ドミナント「V」からトニック「I」につなげることで、結びつきの強い響きとしてトニックへの解決を提示することができます。
2.ツーファイブ型
ダイアトニックコード内の五番目のコード(V)と四番目のコード(IV)はそれぞれ
- V=ドミナント=「不安定」
- IV=サブドミナント=「少し不安定」
という役割を持つ重要なコードとして扱われており、それらをつなげた
F → G(IV → V)
のようなコード進行は、サブドミナントのコードがドミナントに切り替わるスムーズな展開として頻繁に活用されます。
 ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて
ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて
そのうえで、ここでの「F(IV)」を、ダイアトニックコード内で同じくサブドミナントの機能を持つ「Dm(IIm)」に置き換え、
- Dm → G(IIm → V)
とすることで、こちらでテーマとしている強進行の構成を作り出すことができます。
ルート音「D→G(II→V)」は完全4度上行のため強進行となります。
音楽ジャンルによっては、サブドミナントからドミナントへの流れは「IV → V」よりもこの「IIm → V」の方が好まれ、このようなコードの構成は「ツーファイブ」と呼ばれています。
※ツーファイブ解説ページ  ツーファイブとは?(概要と基本的な成り立ち、活用方法、マイナーキーにおける例など)
ツーファイブとは?(概要と基本的な成り立ち、活用方法、マイナーキーにおける例など)
また、マイナーキーにおいては「IIm7」がフラットファイブの形となり「IIm7-5」のようになることがほとんどです。(このあたりの詳しい解説はこのページでは割愛します)
3.他
他にも、ダイアトニックコード内では、以下のコード進行が強進行となります。
- C → F(I → IV)
- Em → Am(IIIm → VIm)
- Am → Dm(VIm → IIm)
まとめ
下記は強進行のまとめです。
- 「強進行」とは「心地良いコードの動き」のことを意味する音楽用語
- ポップス・ロックではコードルート音の完全4度上への動きを指して「強進行」と呼ぶことが多い
- 強進行を活用してドミナントモーションやツーファイブの形を作ることができる
コードのスムーズなつながりを求める場合には、代理コードなどによって強進行の構成を盛り込んでみることを検討してみて下さい。

音楽理論について詳しく知る
 音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る
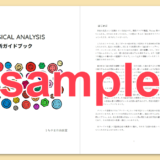 作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ
作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

 著者:
著者: