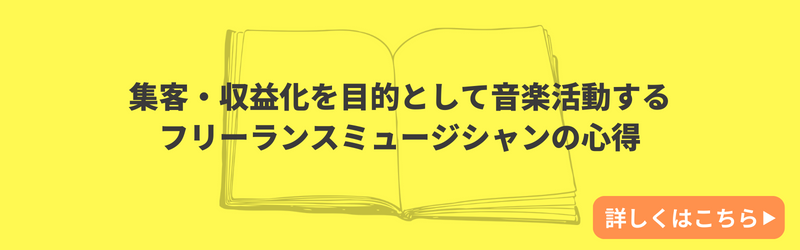作曲やジャズの演奏などでよく耳にする
「ツーファイブ」(またはツーファイブワン)
とは特定のコード進行を指す音楽用語で、とても強い結びつきを持ったこのコードの流れは、さまざまな楽曲において頻繁に扱われます。
こちらのページではそんな「ツーファイブ」の成り立ちや、それが作曲や演奏の中でどのように活用されているか、という点などについて解説していきます。
目次
ツーファイブの概要
ツーファイブ=ダイアトニックコードにおける「二番目→五番目」というコードの動き
ツーファイブを理解するうえで必要となるのが、「ダイアトニックコード」の知識です。
▼「ダイアトニックコード」解説ページ  ダイアトニックコードとスリーコード(概要や成り立ち、コードの役割などについて)
ダイアトニックコードとスリーコード(概要や成り立ち、コードの役割などについて)
上記ページでもご説明している通り、ダイアトニックコードとは
スケールの上に作られたコードのグループ
のことです。
通常、音楽では「キー」という概念のものと、その音使いの土台となる
- メジャースケール(「メジャーキー」を成り立たせる音階)
- マイナースケール(「マイナーキー」を成り立たせる音階)
という存在があり、それらの音を活用して
- 「メジャーダイアトニックコード」
- 「マイナーダイアトニックコード」
が作られます。
今回題材としている「ツーファイブ」とは、このダイアトニックコード内における
二番目のコード→五番目のコード(II→V)
というコードの流れを指すものです。
▼関連ページ  キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉
キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉  メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について
メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について  マイナースケールの解説 ハーモニックマイナー・メロディックマイナーを含む三種について
マイナースケールの解説 ハーモニックマイナー・メロディックマイナーを含む三種について
「自然な響きの変化」と「結びつきの強い音の流れ」をあわせ持つコード進行
以下は例として、「Cメジャーダイアトニックコード(四和音)」にある七つのコードと、それらを活用したツーファイブ(IIm7→V7)の形を示したものです。
[IM7,IIm7,IIIm7,IVM7,V7,VIm7,VIIm7-5]
ここでの「Dm7(IIm7)」および「G7(V7)」のそれぞれは、
- 「Dm7(IIm7)」=サブドミナント(少し不安定)
- 「G7(V7)」=ドミナント(不安定)
に分類される響きを持っており、ツーファイブにあたる「Dm7→G7(IIm7→V7)」は
「サブドミナント→ドミナント」
という自然な響きの変化を生み出します。
さらには、上記「Dm7→G7」にある
「レ(D)→ソ(G)」
というルート音の変化は「完全4度上(または完全5度下)」に向かう音の動きであり、これは
「強進行(結びつきの強い流れ)」
に相当するものです。
つまり、「ツーファイブ」のコード進行には
- 自然な響きの変化
- 強進行
の両方が含まれる、ということです。
このような理由からツーファイブはコード進行の象徴のようなものとして扱われ、特に強い結びつきを持つコードの流れとして様々な場面で活用されます。
▼関連ページ  強進行について(通称「4度進行」=ドミナントモーションの元になる力強い音の動き)
強進行について(通称「4度進行」=ドミナントモーションの元になる力強い音の動き)
ツーファイブワン
ツーファイブにある「V7」は、通常
V7→I(上記例でいう「G7→C」)
という流れによって、トニック(I)につながるものです。
そのため、ツーファイブ(IIm7→V7)のあとにワン(I)を配置した
「IIm7→V7→I」
の形も、「ツーファイブワン」という名称として同じように活用されます。
この「ツーファイブワン」は「サブドミナント→ドミナント→トニック」という三種の機能的なつながりを端的に表したものとしても広く知られています。
四和音・三和音いずれもツーファイブと認識される
ツーファイブを語る際には、上記の通りコードに7度の音(セブンス)が頻繁に付加されます。
特にジャズなどで「ツーファイブ」といえば、この四和音の形(IIm7→V7)を指すことがほとんどですが、もちろん三和音の形(IIm→V)も「ツーファイブ」として扱うことができます。
さらには両者をミックスして、例えば以下のように片方のコードのみを四和音とした形も一般的に「ツーファイブ」として認識されます。
- Dm→G7(IIm→V7)
- Dm7→G(IIm7→V)
上記を踏まえ、こちらでは一般的な四和音の「IIm7→V7」を活用して解説を進めていきます。
▼関連ページ  セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について
セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について
マイナーキーのツーファイブ
「ツーファイブ」はマイナーキーにおいても作り出すことができます。
以下は、「キー=Aマイナー」における「Aマイナーダイアトニックコード」にある七つのコードと、それを活用したツーファイブの例です。
[Im7,IIm7-5,IIIM7,IVm7,Vm7,VIM7,VII7]
こちらでもメジャーキーと同じく「二番目→五番目」というコードの流れによりツーファイブが作られています。
五番目のコードは、上記ダイアトニックコード内では「Vm7(Em7)」でありながらも、ドミナントコードとしての響きを明確にさせるためにツーファイブでは「V7(E7)」として扱われます。
「IIm7」が「IIm7-5」となる
マイナーキーのツーファイブを考えるうえでポイントとなるのは「IIm7-5」という存在で、メジャーキーでは「IIm7」だったものがマイナーキーでは「IIm7-5」となり、
「IIm7-5→V7」
という形でツーファイブが作られます。
前述した「ツーファイブワン」でこれを表せば「IIm7-5→V7→Im」という形となり、つまるところこれは
「マイナーにつながるツーファイブは『IIm7-5→V7』になる」
ということを意味します。
ツーファイブの活用方法
「IIm7」と「V7」はセットで扱われる
ツーファイブ(IIm7→V7)にある二つのコードは既に述べた通り強い結びつきを持っているため、コード進行の中では頻繁にセットで扱われます。
具体的には、
「『V7』の前には『IIm7』があってもいい」
という論理のもとに、「V7」の前に「IIm7」が挿入される形で活用されます。
以下は、「キー=Cメジャー」における「G7(V7)」の前に「Dm7(IIm7)」を挿入した例です。
挿入後:C→Am→Dm7-G7[I→VIm→IIm7-V7]
ここでは、「G7(V7)」を「Dm7→G7(IIm7→V7)」として分割するようにツーファイブが活用されています。
このようなアイディアはリハーモナイズの一種として頻繁に活用されます。
▼リハーモナイズ解説ページ
 リハーモナイズの解説|概要と考え方、やり方や実例などを詳しく説明します
リハーモナイズの解説|概要と考え方、やり方や実例などを詳しく説明します
その他コードへの活用
上記アイディアはドミナントセブンス(V7)としての働きを持つコードのすべてに流用できます。
以下は同じく「キー=Cメジャー」において、「セカンダリードミナントコード」を含む構成にツーファイブを適用した例です。
挿入後:C→Bm7-5→E7→Am[I→VIIm7-5→III7→VIm]
この例では、セカンダリードミナントコード「E7」とその後のコード「Am」を
「V7→Im(E7→Am)」
と見立てて、「ツーファイブワン」の形となるよう直前に「Bm7-5(VIIm7-5)」を挿入しています。
前述の「Aマイナーダイアトニックコード」の例でご説明した通り、「V7→Im(ファイブワン)」がマイナーに着地していることから、ここでは「IIm7-5」が活用されているところがポイントです。
このように、ツーファイブの向かい先が「メジャー/マイナー」のいずれかによって、「ツー(II)」にあたる部分を「IIm7」とするか「IIm7-5」とするかが変わります。
また、上記はあくまで基本的な例で、マイナーに着地するツーファイブの構成で「IIm7」が活用される例もあります。
▼関連ページ  セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します
セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します
まとめ
以下は、「ツーファイブ」のまとめです。
- 「ツーファイブ」とは、ダイアトニックコードにおける「二番目→五番目(II→V)」というコードの流れを指すもの
- ツーファイブの流れは「自然な響きの変化」と「結びつきの強い音の流れ」をあわせ持つ
- マイナーにつながるツーファイブは「IIm7-5→V7」になる
- ツーファイブはセットとして、「V7」の直前に「IIm7(またはIIm7-5)」を挿入するように活用される
いろいろな曲のコードに数多くのツーファイブが含まれているため、曲分析を通してその使いどころを確認してみて下さい。


 著者:
著者: