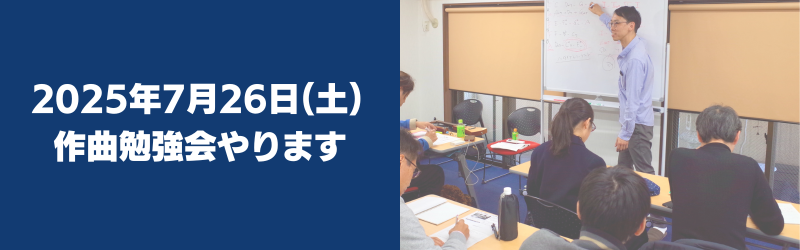こちらのページでは、コード進行を締めくくるための概念である「終止(しゅうし)」について、その詳細と種類、および使用例などについて解説していきます。
終止の概要
終止とは?
「終止」とは広い意味で、
「ハーモニー=コード進行(和声)がある程度展開したのち一旦落ち着くこと」を表す言葉です。
ポップス・ロックにおいて、通常コードは機能的な流れに沿ってつながり、どこかでその流れは一旦落ち着きます。
その「落ち着くこと」そのものを指して「終止」と呼んだり、「落ち着かせ方」の手法をいくつかの種類に分けて「〇〇終止」と呼んだりします。
ダイアトニックコードとコード機能の理解が必要
終止を理解するためには、「ダイアトニックコード」とそれぞれのコードが持つ響きの役割(機能)について把握しておく必要があります。
前述したように、終止は「コード進行の落ち着き」に関わる概念であるため、コード進行の「響きの展開」を生み出す、「安定」「不安定」「一時不安」の三種の役割を知っておく必要がある、ということです。
終止の種類
これ以降は代表的な終止の種類について解説していきます。
1. 全終止
まずひとつ目にご紹介するのは、終止の象徴ともいえる「全終止」です。
全終止はダイアトニックコードにおける「V→I」というコードの進み方を指す終止の形です。
以下は「キー=Cメジャー」における全終止の例です。
C→F→G→C(I→IV→V→I)
不安定を安定につなぐ、最もスタンダードな形
前述のページでも解説している通り、ダイアトニックコードにおける一番目のコード(I)は安定した響きを持ちます。
一方、五番目のコード(V)は不安定な響きを持つため、その「不安定さ」が「安定」を連想させます。
それを踏まえ、コードの流れを「V→I」とつなげることでリスナーに程よい安心感を与え、「コード進行の落ち着き」を感じさせるのが全終止の仕組みです。
全終止は「終止」という言葉の意味そのものになることもある
この全終止の形はあまりに結びつきが強く納得感があるため、ポップス・ロックにおいて「終止する」という言葉を使う場合、直接的にこの全終止の形を指すことも多いです。
また同じ理由から、なんらかのコードの流れをきちんと締めくくりたい場合には全終止の形を用いるべきで、それによりリスナーは「コードの流れが終わった」という印象をそこから受けることになります。
全終止は定番であり、多用するとリスナーに「平凡な構成」という印象を与えてしまうことにもなりかねないため、これを回避するために、一般的にはこれ以降でご紹介するさまざまな終止が適度に取り入れられます。
2. 偽終止
二つ目にご紹介するのは、「偽終止(ぎしゅうし)」という終止の形です。
偽終止は、全終止の形を変形させリスナーにそれとは違った雰囲気を感じさせるものです。
以下は上記の例と同じく、「キー=Cメジャー」における偽終止の形を示したものです。
C→F→G→Am(I→IV→V→VIm)
不安定を「I」以外につなぐ
前述した「全終止(V→I)」は結びつきが強く、リスナーは潜在的にその流れ予測しながらハーモニーを聴いています。
偽終止はそれを裏切るような効果を狙ったもので、上記の例ではダイアトニックコード内において「C(I)」に似た響きを持つ「Am(VIm)」を活用し、「~G→Am(V→VIm)」という流れを作り出しています。
これにより、リスナーは
「『G』が鳴った」→「『C』が来るだろうな」→「来なかった」
という驚きのようなものをそこから感じることになります。
解釈次第でいろいろな偽終止が作れる
上記例における「Am(VIm)」は「C(I)」と同じく安定した響きを持つため、「~G→Am(V→VIm)」というコードの流れによって本来の全終止(V→I)が持っている「不安定→安定」という響きの展開が維持されます。
そのような意味から、全終止を「I」以外のコードへの展開として応用するとき、その最有力候補として特にこの「V→VIm」の形が多用されています。
またそれ以外に、以下のような構成も偽終止として扱われることがあります。
- V→IIIm(G→Em)
- V→VI(G→A)
これらを踏まえると、広義での偽終止は
「『I』に似た構成音や機能を持ったコードを『V』の後につなげてコードの流れを落ち着かせること」
とも解釈することができます。
3. アーメン終止(変終止・サブドミナント終止)
最後にご紹介するのが「アーメン終止」(変終止・サブドミナント終止)です。
これは、全終止「V→I」における「V」を別のコードに置き換える終止の形です。
以下は「キー=Cメジャー」におけるその例です。
C→Am→F→C(I→VIm→IV→I)
弱い不安(一時不安)から「I」への終止
「サブドミナント終止」という名前の通り、この終止では「V」の代わりに「一時不安=サブドミナント」の機能を持つ「IV」を活用し、「IV→I」という流れを作ります。
この「IV」は「V」ほど響きが不安定ではないため、全終止に比べて「静かに落ち着いた」「なんとなく落ち着いた」という印象をリスナーに与えます。
同じ理由から「V→I」が持つドラマチックな響きが弱まり、少し都会的な雰囲気が生まれるのもこの終止の特徴の一つです。
アーメン終止の変形「サブドミナントマイナー終止」
あわせて、上記「アーメン終止」に関連する特殊な終止として、サブドミナントマイナーコードから直接トニックに落ち着く「サブドミナントマイナー終止」の形も、ポップス・ロックではよく活用されます。
以下は、同じく「キー=Cメジャー」における例です。
C → Am → F → Fm → C(I → VIm → IV → IVm →I)
アーメン終止と同じく「V」を排除し、「IV」の代わりにサブドミナントマイナーコード「IVm」から「I」へ終止する流れが作られています。
こちらも「静かな落ち着き」という印象は保たれ、かつノンダイアトニックコードがコードの流れを締めくくる部分に登場することで、個性的な響きが生まれています。
まとめ
以下は「終止」のまとめです。
- コード進行が落ち着くことを「終止」と呼ぶ
- 代表的な「全終止」の形と、それ以外にいくつかの種類がある
- 全終止が定番として多用されるため、曲調に応じてさまざまな終止の形を選べるようになると理想的
作曲に慣れないうちは基本的に全終止を活用し、まずは「コードの流れを落ち着かせること」を体感してみて下さい。
その次のステップとしていろいろな終止を作曲に導入していくことで、それぞれが持つ響きの特徴を把握できるようになっていくはずです。
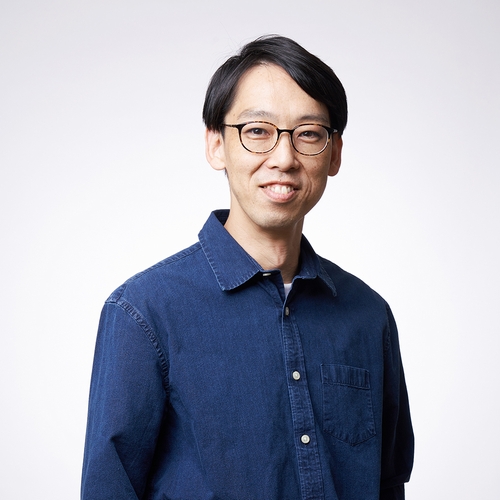
「サブドミナントマイナー終止」はサブドミナントコードの使用例として定番ともいえるものです。
音楽理論について詳しく知る
 音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る
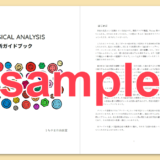 作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ
作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

 著者:
著者: