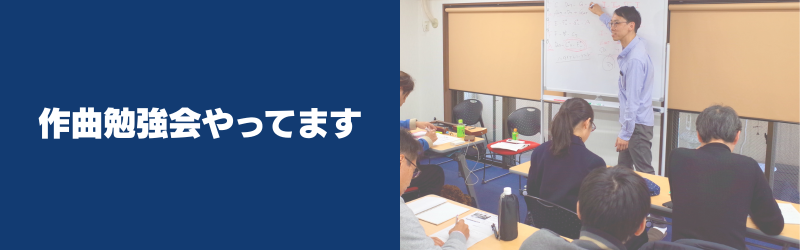コード進行にはいろいろな種類がありますが、その中でも最もポピュラーで、さまざまな曲に活用されている「カノン進行」と呼ばれる型があります。
こちらではその成り立ちと、曲への活用、アレンジ方法などについて解説していきます。
カノン進行とは?
こちらでテーマとして取り上げる「カノン進行」とは、一般的にクラッシック曲「パッヘルベルのカノン」(以下動画)で扱われているコード進行のことを指すものです。
こちらの動画は「キー=Dメジャー」となっていますが、これをわかりやすく「キー=Cメジャー」で表すと
のようなコード進行となります。
このコードの流れには、後述するいくつかの理由から美しく、かつ親しみやすい雰囲気があるため、それらがさまざまな曲に活用されコード進行として広く認知されています。
ポイントは構成音の綺麗なつながり
第一に、このコード進行のサウンドが心地良いと感じられる理由は、構成音が順次進行によって綺麗につながっているところにあります。
以下は冒頭四つのコードとその構成音を左から並べたものです。
| C | G | Am | Em |
| ド ミ ソ |
ソ シ レ |
ラ ド ミ |
ミ ソ シ |
これを見ると、赤太字部分の構成音が
というつながりを生んでいることがわかります。
メジャースケールを中心音から順番に下げる流れ
この例における「キー=Cメジャー」とは、「ド」を中心音とした
の音をメインに活用する音楽のことを意味します。
そこから、上記「ド→シ→ラ→ソ」という音階の変化は
だと解釈できます。
このような音の動きを含んでいる点が、カノン進行の最大の特徴です。
▼関連ページ
 メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について
メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について  キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉
キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉
循環コード的な構成になっている
また、カノン進行を考える際にはそれが「循環コード」のような構成になっているという点にも着目できます。
▼関連ページ
 循環コードの詳細と成り立ち・派生形や「逆循環コード」についての解説など
循環コードの詳細と成り立ち・派生形や「逆循環コード」についての解説など
上記のページでも述べているように、「循環コード」とは「循環させることができるコード進行」のことを指す言葉です。
例えば「キー=Cメジャー」における
などはその代表例ですが、この構成のポイントは
- 冒頭に安定した響きを持つコード(C)がある
- 末尾に不安定な響きを持つコード(G)がある
- 全体を通して、機能的にスムーズなコードのつながりがある
という点です。
つまり、冒頭にあるどっしりとした響きを持つコードがさまざまに表情を変えて不安定な末尾のコードに行き着き、それがまた冒頭のコードを連想させる構造になっているということです。
循環コードの機能的おさらい
循環コードを理論的に解釈するためには、ダイアトニックコードの機能やカデンツに関する知識が活用できます。
▼関連ページ
 ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて
ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて
コードの機能は大きく
- 安定=トニック(T)
- 不安定=ドミナント(D)
- 一時不安=サブドミナント(SD)
に分類されますが、上記でご紹介した循環コードの典型的な形は
T→T→SD→D
という機能のつながりとなっています。
カノン進行の循環コードによる解釈
ページ冒頭でご紹介したカノン進行の例を、同じように「循環コード」の観点から確認すると、そこにも同じように
- 冒頭の「C」(I)コード
- 末尾の「G」(V)コード
- 機能のスムーズなつながり
があることがわかります。
以下は、カノン進行に機能的解釈を併記したものです。
(T→D→T→T→SD→T→SD→D)
これを見ると、要所要所でトニックへ回帰しつつも、構成の最後では「SD→D」という流れによってコード進行の推進力が生み出されています。
カノン進行のポイントまとめ
ここまでを一度まとめると、カノン進行を親しみやすいものだと感じる理由は以下の二点にあるということがわかります。
- 構成音のスムーズなつながり
- 推進力のある機能的なコードのつながり
すなわち、これらが「カノン進行らしさ」を生み出しているものです。
カノン進行が使われた曲
ここまでにご紹介した通り親しみやすい響きを持ったカノン進行ですが、実際のところ多くの曲ではカノン進行をアレンジする形で使用されています。
カノン進行をほぼそのまま活用した曲の例
もちろん、前述したカノン進行の構成をほぼそのまま使用して曲にしている作品もあり、例えばグリーン・デイの「Basket Case」などはその好例です。
本作は彼らの代表曲ともいえる楽曲ですが、この曲の冒頭のコード進行は
であり、これは本ページの一番初めにご紹介したカノン進行を「キー=Dメジャー」で表現したものとほぼ同じです。
それでも、バンドアレンジによって「パッヘルベルのカノン」から感じられる優雅な雰囲気は無くなり、親しみやすさだけが残っているという印象を受けます。
このように、いろいろなサウンドに活用できてしまうところがカノン進行の魅力でもあります。
カノン進行のアレンジ型:四つ目のコードをセブンスにする
また、オアシスの代表曲「Don’t Look Back In Anger」もカノンを活用した曲として知られています。
こちらの曲は「キー=Cメジャー」で、Aメロのコードは
のようにつながっており、こちらもご紹介していたカノン進行の構成とよく似ています。
ポイントとなっているのは四つ目のコード「E7」で、これはもともとのカノン進行にある「Em」をセブンス化したものです。
これにより「Em=ミ・ソ・シ」という構成音が「E7=ミ・ソ#・シ・レ」と変わり、もともと
とつながっていた構成音が
に変形しています。
ここで生まれている「ソ#」はCメジャースケールに含まれない音であるため、その部分に異質な雰囲気が生まれ、そこがコード進行のアクセントとなっています。
こちらは、カノン進行にワンポイントのアレンジを加えた構成として解釈できます。
カノン進行のアレンジ型:四つ目のコードを他のコードにする
また他にも、コードそのものを違ったものに差し替えてしまうやり方もあります。
例えば、ビートルズの「Let It Be」などはその典型例です。
この曲(キー=Cメジャー)は、Aメロの冒頭のコードが
のようになっていますが、これは前述した「Don’t Look Back In Anger」と同じく四つ目のコードをアレンジしているケースです。
こちらでは根本的に「Em」というコードを回避し、「F」のコードが配置されています。
これによって
とつながっていた構成音の流れは
のような形となり、こちらも同じくカノンの響きの裏をかいているような印象をリスナーに抱かせます。
カノンの骨組みを残し部分的にアレンジする
上記二つの例以外にも、挙げるときりがないほど沢山の曲にカノンの進行やそれをアレンジしたコード進行が活用されています。
特にアレンジ型に至っては、いわゆる「カノン」らしい響きや流れを裏切るところに重きを置いているものが多く、それが曲の個性につながっています。
傾向としては、上記の例のように前半の数コードのみカノンと同じ流れを提示しつつ、四つ目か五つ目のコードでそれを独自の構成にアレンジする、というやり方が多いです。
もちろんカノン進行のアレンジにはさまざまなケースがありますが、やはりある程度骨組みを残しておかないと、それはもはや「カノン進行」とは呼べなくなってしまいます。
カノン進行をもとにコードを構成させる場合、
- カノン進行の基本となるコード進行を知ること
- それらの骨組みを残しつつ、途中からオリジナルな展開をそこに加えること
を行うことで、親しみやすさを残しつつ、個性的な響きを盛り込むことができるはずです。
※カノン進行を活用したその他の曲については、以下のページでもまとめています。
 「カノン進行」によって作られている洋楽曲をもとに、そのいろいろなバリエーションを勉強する【全13曲】
「カノン進行」によって作られている洋楽曲をもとに、そのいろいろなバリエーションを勉強する【全13曲】
まとめ
ここまでカノン進行に関連して、その詳細と活用例等を解説してきました。
上記で取り上げたように、さまざまな曲をカノン進行の観点から分析し、そのアレンジの仕方や構成音のつながり等を紐解くことで、それを作曲にどう活かしていけばいいかが理解できるはずです。
まずは楽器などで代表的なカノン進行の形を鳴らして、スムーズなコードのつながりとその響きを体感してみて下さい。

音楽理論について詳しく知る
 音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る
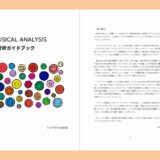 作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介
作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介

 著者:
著者: