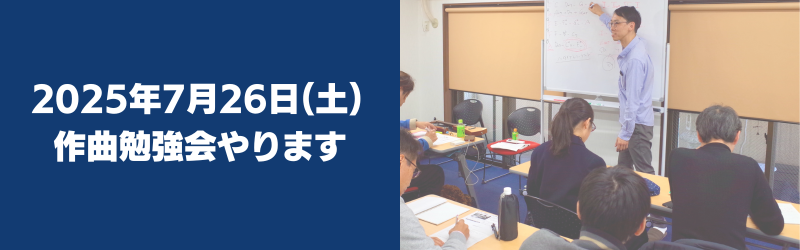こちらのページでは、普段作曲の先生として活動している私が実際に読んでおすすめできると感じた音楽理論関連の本を9冊ご紹介します。
作曲はもちろんのこと、演奏にも役立ててもらえると嬉しいです。
目次
ポピュラー系
「コード理論大全」
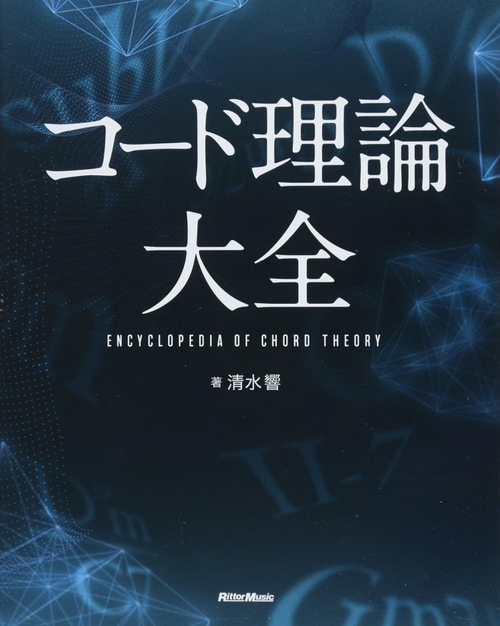
まず初めにご紹介するのが「コード理論大全」です。
タイトルにある通り、こちらはコードやコード進行に関する理論的な内容をまとめた書籍です。
ページ数が多く、標準的な大きさでありながら辞書のような存在感があります。
内容は理論的な事柄を順序に沿って淡々と述べていくような構成になっており、教科書に近い「硬派な理論書」という印象を受けました。
真面目に、かつコードに関する知識をきちんと吸収したい方には特にお勧めできます。
反面で、説明に親しみやすさを求めていたり、楽しみながら読み進めたい人には少し敷居が高いかなとも思えました。
既に少し知識を持っている人向け
この書籍ではコード進行の分析(アナライズ)についても言及されており、同じく曲分析を重視する自分にとってはその点に親しみをおぼえました。
解説はとても丁寧なのですが、それらを実用につなげるにはある程度の想像力が必要になりそうです。
そのような意味から、既に少し知識を持っている人がさらなるステップアップや知識固めのために読む本だといえるかもしれません。
このあたりは「理論書」という性質上難しいところがありますが、各章の終りには練習問題も掲載されており、著者の配慮が感じられます。
「ザ・ジャズ・セオリー」
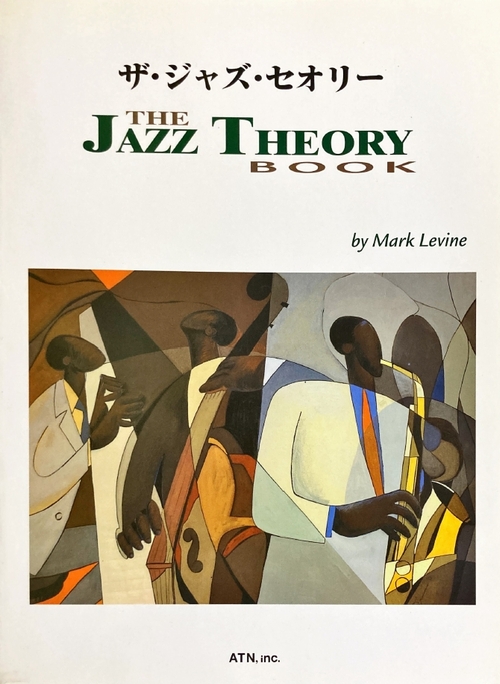
次にご紹介するのが、海外の音楽理論書として有名な「ザ・ジャズ・セオリー」です。
いわゆる現代のポピュラー音楽理論の基礎になっているともいえる、バークリー系(ジャズ系)の音楽理論を扱っている本として必ず話題にあがる一冊です。
ページ数は500ページ近く、そして大型本で手に持つとずっしり重いです。
お値段も結構高いので買うのに躊躇してしまいますが、中身は本物でポピュラー系(ジャズ系)の音楽理論はほぼ網羅されていると感じます。
譜例が豊富
私が個人的に好感を持っているのは、譜例が沢山掲載されているところです。
題材となっているのはほとんどがジャズの有名曲ですが、解説されている理論の実例が五線譜で掲載されています。
さらには曲タイトルに加えてアーティスト名やアルバムタイトル等も併記されているので、ネットやサブスク音楽サービスなどで簡単に調べて音源を確認することができます。
また語り口はソフトで優しいので、机の上にこの本を広げてゆっくり読み進めているとまるで個人レッスンを受けているような気分になります。
この本の性質を理解している人におすすめ
本書の内容は濃く、確かに素晴らしいのですが扱われているテーマが高度で、ある程度の知識を持った人でないと読破するのは難しいかもしれません。
また、上記で述べた通り本書は洋書の翻訳本で、かつ解説にも若干のクセがあります。
マイナーセブンスコードを「〇-7」と表記したり、「チェンジ」や「ヴァンプ」などのジャズ(バークリー?)用語が多用されていたり、この本特有の表現があって慣れも必要です。
この本の実際のところを以下のページでも詳しく解説しているため、気になる方はそちらも是非参考にしてみてください。 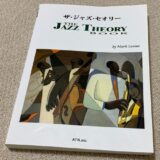 「ザ・ジャズ・セオリー」(マーク・レヴィン著)のレビュー
「ザ・ジャズ・セオリー」(マーク・レヴィン著)のレビュー
「ジャズセオリーワークショップ」
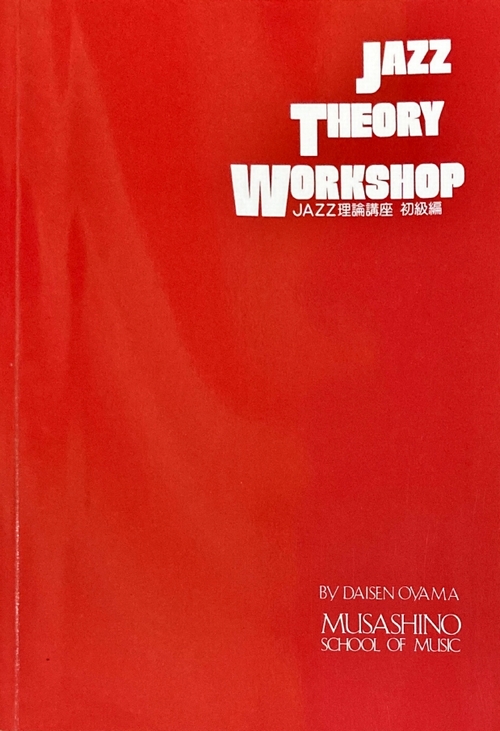
次にご紹介するのは、現在はもう無くなってしまった「武蔵野音楽学院」という音楽学校からリリースされている音楽理論書、「ジャズセオリーワークショップ」です。
上巻・下巻による構成で、ポピュラー音楽に活用できる理論が丁寧に解説されています。
前述の「ザ・ジャズ・セオリー」がいかにも海外(バークリー)的であるのに対し、こちらは日本的で初心者でもとっつきやすい内容になっていると感じられます。
見た目はちょっと古めかしい、けれど中身は親しみやすい
1970年代頃の本であるため印刷からはなかなかの歴史が感じられますが、内容は確かなものです。
またミニドリルも掲載されており、それらを活用することで学んだ知識を定着させることができます。
上巻は「初級編」ということで根本的な部分から解説されており、下巻では「中上級編」として少し高度な内容まで扱われています。
上下あわせて購入したい良書です。
「実践コード・ワーク 完全版 理論編」
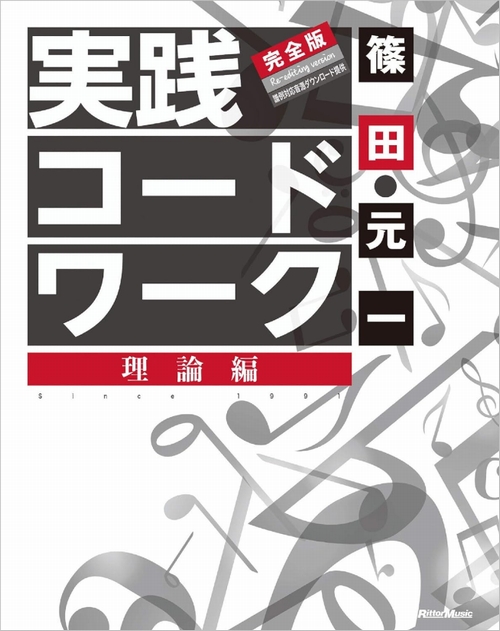
次にご紹介するのは、ポピュラー音楽系理論書の分野においてロングセラーとなっている「実践コードワーク」の理論編です。
コードの成り立ちやコード進行の基礎的な扱い方、ノンダイアトニックコードやテンションコードなど、コードとコード進行に関するさまざまなことが語られています。
キーボード奏者である篠田元一さんによる書籍であるためジャズやキーボード的観点からの解説も多いですが、実例を多数掲載することで表面的な説明にとどめず、より実践的なアイディアを優先して紹介しているところに好感が持てます。
「ボイシング」についての解説がある
上記の他に「転調」「スケール」「モード」などについても記載があり、あわせて「ボイシング」についても解説があるなど編曲につながる高度な知識も学ぶことができます。
音楽を作ったりアレンジしたりする際の基礎知識として常に手元においておき、何度も読み返しながら活用することで理解を深めていくことができるはずです。
一時期、廃刊のため手に入りづらくなっていましたが、先日無事に復刊して入手できるようになりました。
「憂鬱と官能を教えた学校」
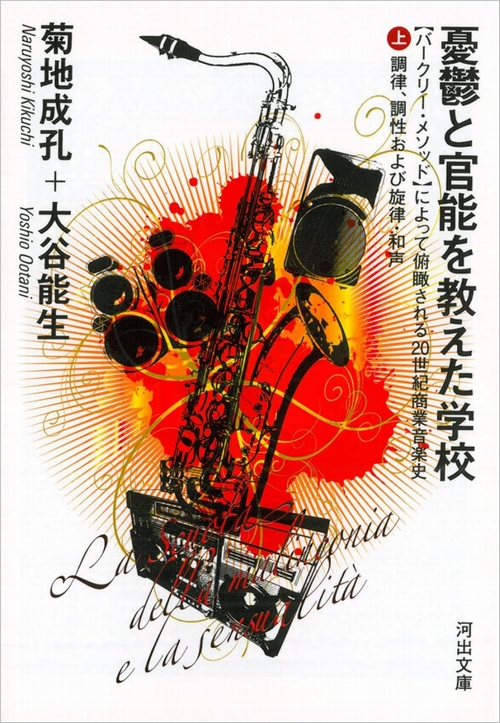
ポピュラー系の音楽理論書として最後にご紹介するのが「憂鬱と官能を教えた学校」です。
ジャズミュージシャンとして有名な菊地成孔さんによる、バークリー理論解説の書籍です。
こちらはいわゆる理論書というよりも、理論の講義を書籍として書き起こしたような内容となっています。
語りと同じ文体には親しみやすさがありますが、裏を返せば取り留めのない方向に話が飛んでしまっている部分も多々あり、硬派な理論書を求めている人にはあわないと感じられるかもしれません。
とはいえ、扱われている内容はきちんとしたポピュラー音楽理論で、音律や音そのものの成り立ちを土台として基礎から丁寧に解説されています。
ポピュラー音楽理論の一冊目としてもあり
コードと同じくスケールについてもしっかりとページが割かれているあたりは、やはりバークリー理論系の書籍、といったところです。
一般的な読み物にも近い作風であるため、理論書に慣れていない人が「さあ理論を勉強するぞ」と構えることなくとりあえず読んでみる、という向き合い方もできると思います。
こちらも上下巻あります。
クラシック系
「音楽の理論」
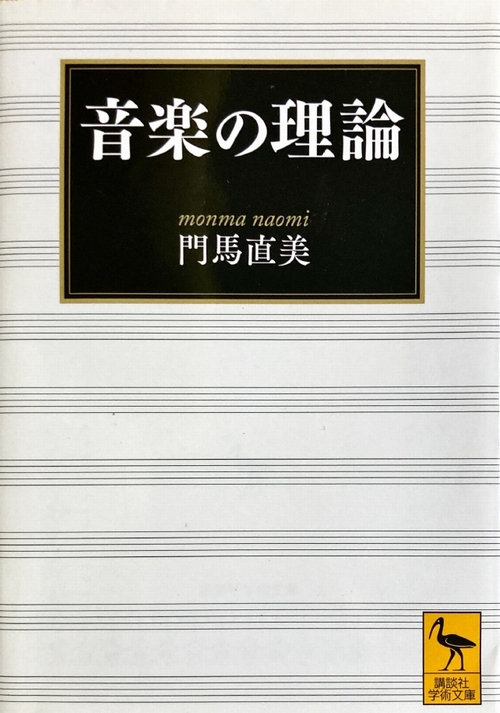
クラシック系の音楽理論書としてご紹介できるひとつめは、その名のとおり「音楽の理論」という名前の書籍です。
この手の本にしては珍しく文庫本のサイズとなっており、持ち運びや、気軽に手にとれるという意味でも思いのほか重宝します。
また、内容は楽典をより作曲・演奏のために詳しく掘り下げたようなもので、予備知識が無い人にとっては少し高度かなとも感じられますが、理論書としての総合的な評価としてこちらに加えました。
昭和30年に初版が刊行されたという書籍ですが、内容からは古さが感じられません。
音楽理論のほとんどが載っている
この本をご紹介するうえで特筆すべきは、譜例の多さと内容の網羅性です。
ひとつのテーマを解説するにあたり必ず譜例を掲載し、それぞれについてしっかりとページを割いています。
また、クラシックを対象としていながらも音楽に関するほとんどのことが扱われており、この一冊を繰り返し読むだけで音楽理論について深い知識が得られるはずです。
「ちゃんとした音楽理論書を読む前に読んでおく本」
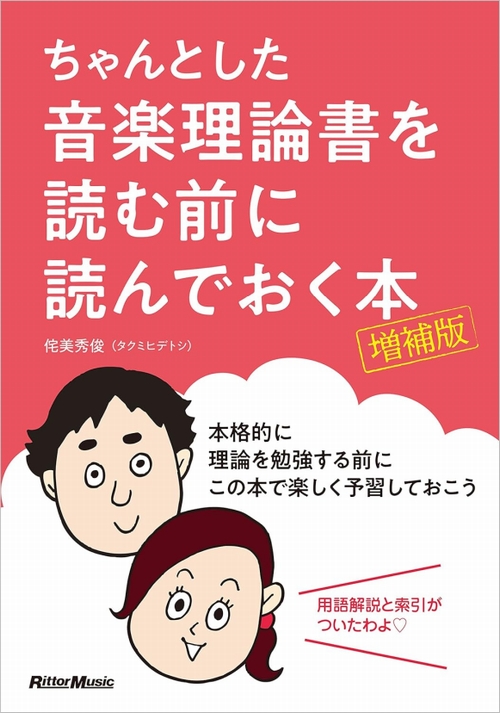
硬派な音楽理論書に抵抗がある人にお勧めしたいのが、こちらの「ちゃんとした音楽理論書を読む前に読んでおく本」です。
一応「クラシック系」に分類していますが、ポピュラー理論的目線とクラシック理論的目線の両方から解説されています。
扱われている内容は「音程」「音階」「調性」など楽典にも通じるもので、二人の登場人物によるセリフの掛け合いによって漫画を読むような感覚でそれらを学ぶことができます。
親しみやすさに配慮されているので、音楽の知識がほとんどなくても読み切ることができるはずです。
優しすぎず、かつ難しくない
入門書といえども初心者にとって十分な内容であるため、ここで得た知識をもとにもう少し高度な理論書にステップアップする、という手順で活用することもできるでしょう。
「高度な理論書」と「超入門書」の中間に位置するようなこの手の書籍は案外見つからないため、そのような意味からも初心者の人には重宝するはずです。
「新版 楽典 音楽家を志す人のための」
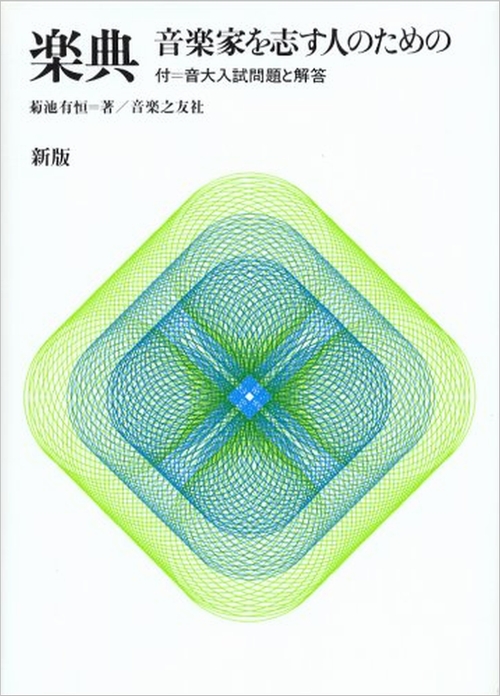
次にご紹介する書籍は正確には「楽典」に分類されるものでありながらも、音楽理論書に近い部分もあり、また評価も高いためこちらに加えました。
音大向けのスタンダードな楽典といえば、「黄色い楽典」とも呼ばれる「楽典 理論と実習」が有名ですが、歴史ある書籍のため「現在の音楽に合わない解説がある」「説明がわかりづらい」などの声も挙がっています。
そんな中で、本書ではタイトルにもある通り「音楽家を志す」というテーマのもと、楽典の内容がさらに実践的なものに落とし込まれてわかりやすく解説されています。
楽典でありながらポピュラー音楽にも流用できる
特に3章以降は作曲や演奏に活用できる内容が多く掲載されており、ポピュラー音楽でいうところの「スケール」と「コード」につながる基礎的な知識を強化するのに役立ちます。
問題もついているため、それらを解くことで自分で理解度を確認することもできます。
「音楽の基礎」
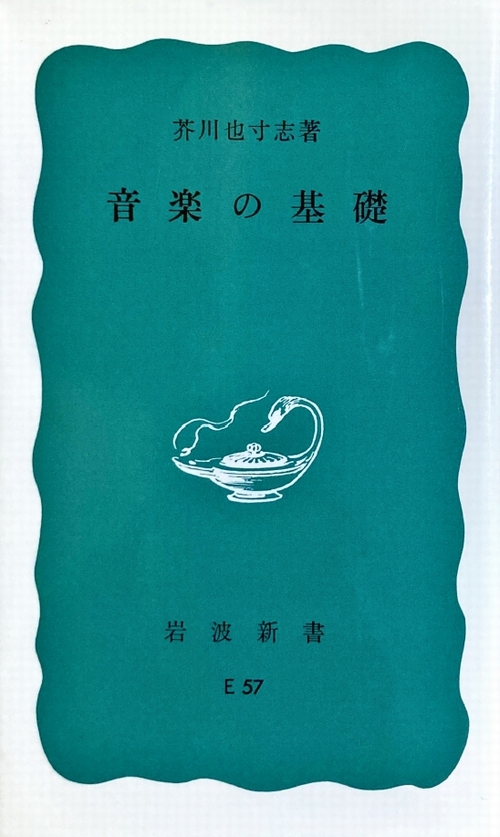
最後にご紹介するのが、芥川也寸志さんが書いた「音楽の基礎」です。
新書サイズの音楽書で、こちらも一般的な音楽理論書というよりは楽典に近い内容ですが、基礎を固める意味でとても勉強になります。
文体はどことなくコミカルで、語り口も軽快なので読み物としても楽しめます。
ページ数が少なく、わりとスムーズに読めてしまうため音楽理論の入門書としてもお勧めできます。
「静寂」の考察は一読の価値あり
個人的に好きなのは、本書の一番初めが「静寂」という章から始まっているところです。
音楽理論書でありながら「音が無い」という状態に対する考察を何よりも先に扱っている、というのはなんとも挑戦的だと感じます。
作曲家でもある著者の音楽的な教養の深さが感じられる本です。
補足
以下のページでは「音楽理論」と「楽典」の違いについて解説しています。
 「音楽理論」と「楽典」の違い 【音楽理論=音楽の構造や成り立ち、楽典=音楽関連の各概念や用語の意味】
「音楽理論」と「楽典」の違い 【音楽理論=音楽の構造や成り立ち、楽典=音楽関連の各概念や用語の意味】
まとめ
ここまで音楽理論系の本を9冊ご紹介してきました。
ポップス・ロック系の音楽理論というと、どうしてもジャズ系(バークリー系)の理論に代表されるような「コード」「スケール」というところに話がいってしまいがちです。
しかし、そもそもそれらを理解するためには楽典で扱われているような基礎的な知識が求められるもので、それによって理解のスピードも変わってきます。
両方の書籍を上手に活用しながら、自分のレベルに合わせて無理なく音楽理論を習得していけると理想的です。

音楽理論について詳しく知る
 音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る
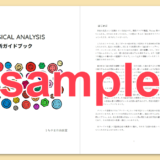 作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ
作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

 著者:
著者: