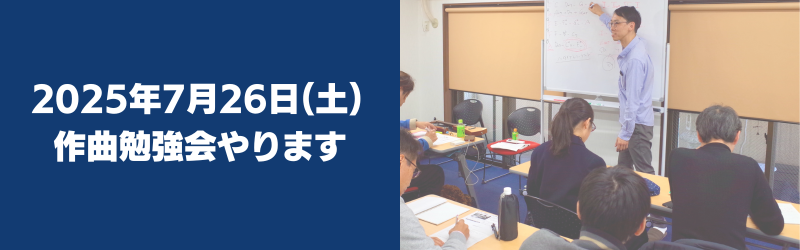作曲初心者の人にとって、
という悩みは定番ともいえるものです。
こちらではその「ダサい」をどう改善させたり、そんな悩みをどう乗り越えていけばいいか、という点について考えてみます。
自分の作る曲が「ダサい」の正体と基本的な考え方
「ダサい」の中身
まず、こちらで取り上げている「ダサい」という表現の意味するところは人それぞれかと思いますが、より具体的には作った曲が
- シンプルで幼稚
- どこかで聴いたような感じ
- 面白みが感じられない
などの状態にあることを指すはずです。
これらは、
- 聴きごたえがない=聴いていてつまらない
- 何度も聴きたいと思えない=曲に愛着が持てない
- 誰にでも作れそう
という評価につながってしまいますが、せっかく作った曲がこのようなものだと感じられてしまうのはやはり切ないです。
「普通」をアレンジして個性を盛り込む
ピアノの鍵盤(以下図)が「白鍵=7個、黒鍵=5個」=計12個から成り立っているように、そもそも音楽で扱われる音には12種類しかありません。
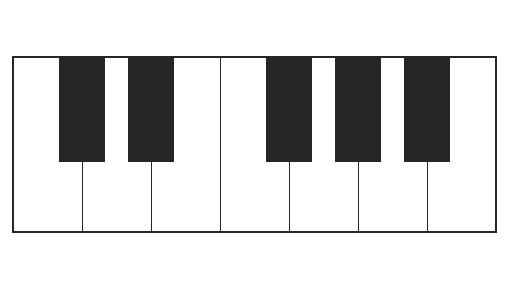
白鍵7個+黒鍵5個=12個
また、リズムの表現にも限りがあるため、何も考えずただ音をつなげるように作曲すると、曲はどうしてもありきたりで聴きごたえの無いものになってしまいます。
これを踏まえ、「ダサい=聴きごたえがない」を改善するためには
がひとつの目安となります。
「ダサい」を改善するためにまず「普通」を知る
音使い(メロディの音階・コード)についてのおさらい
上記でも述べているとおり音楽で扱われる音は12種類で、さらに一般的な曲では
- 「メジャースケール」
- 「マイナースケール」
と呼ばれる音の枠組みに沿って、その12音から「まとまりを感じる7音」を選んで活用します。
▼関連ページ
 メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について
メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について
 マイナースケールの解説 ハーモニックマイナー・メロディックマイナーを含む三種について
マイナースケールの解説 ハーモニックマイナー・メロディックマイナーを含む三種について
そのうえで、曲には「キー」という概念があり、それによって
「どんな音を中心音としたスケール=7音を活用するか」
が定義されます。
それぞれの詳しい解説は上記ページに譲りますが、「キー=Cメジャー」「キー=Eメジャー」を例にすると、
=ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ(中心音「ド」)
Eメジャースケール
=ミ・ファ#・ソ#・ラ・シ・ド#・レ#(中心音「ミ」)
という7音から
=「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の7音を主に活用する音楽
「キー=Eメジャー」の音楽
=「ミ・ファ#・ソ#・ラ・シ・ド#・レ#」の7音を主に活用する音楽
というような定義が成立します。
さらには、コードにはこれらの音をそのままコードに置き換えた「ダイアトニックコード」と呼ばれるコードのグループが活用されます。
=「C・Dm・Em・F・G・Am・Bm-5」
「Eメジャーダイアトニックコード」
=「E・F#m・G#m・A・B・C#m・D#m-5」
▼関連ページ
 キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉
キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉  ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて
ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて
残りの5音も活用できる
もちろん音の種類は全部で12音であるため、残りの5音も曲の中で活用していくことができます。
ただそれらはあくまでも「キー」以外の音であり、「曲のまとまり」を考えるとスケール内の7音を使うことが主流となります。
ここまでに述べた内容が、いわゆる「メロディ(スケール=音階)」と「コード」における「普通」を表現するための知識だといえるでしょう。
リズムについてのおさらい
曲に扱われているリズムには大きく「二拍子」「三拍子」「四拍子」などがあり、中でもポップス・ロックにおいては四拍子のリズムが最も多用されます。
さらには、扱われる音符によって拍子をどう表現するかが変わり、具体的には
- 全音符
- 2分音符
- 4分音符
- 8分音符
- 16分音符
- 連符
などによって、音のアクセントを引き延ばしたり、細かくしたりすることができます。
それらによって
- ターアーターアー…
- タンタンタンタン…
- タタタタ…
- タカタカ…
というようなリズムを持ったフレーズが生み出され、それらを伴奏やメロディに導入することで場面転換や曲の持つスピード感(テンポ)、ノリなどを生みだすことができます。
▼関連ページ
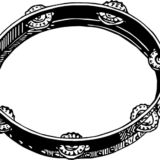 作曲に活用できるリズムの種類(曲作りの幅を広げる)
作曲に活用できるリズムの種類(曲作りの幅を広げる)
組み合わされる音符、休符など
基本的に、ポップス・ロックにおける「拍子」は曲の中で統一されますが、音符の種類はさまざまに組み合わされます。
上記で述べたのはあくまでも基本となる一例ですが、これ以外にも「休符」という概念があり、作曲をするうえでは
「メロディの無い部分(空白)」をいかに盛り込むか
という点も考慮すべきです。
このあたりが、リズムに関する「普通」を表現することにつながる知識です。
「ダサい」を改善するアイディア
上記で簡単に解説した
「『メロディ』『コード』『リズム』の普通」
をもとに、それを超越して、曲を普通ではないもの(=個性的なもの、ダサいと感じにくいもの)にしていくためのアイディアを考えてみます。
1. メロディ:スケール外の音を使う
まず、既に述べた通り曲は「キー」という概念のもと、そのキーにおける「スケール」に含まれる7音を主に活用していきます。
上記で例として挙げた通り、「キー=Cメジャー」というとき、そこでは「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」という7音が活用されます。
例えば、
というようなメロディは、単にスケールの中の音を、中心音「ド」から順番に「ド→レ→ミ」となぞっているだけであるため、そこからは「個性的だ」という雰囲気が感じられません。
ここでアイディアのひとつとなるのが「スケール外の音を使う」というやり方で、具体的には
「キーの音」に含まれない音(この例でいう「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」に含まれない「ド#」「レ#」など)をメロディに盛り込むこと
を意味します。
例えば上記の例を
とアレンジするだけでも、そこからは少し異質な雰囲気が生まれ、それが個性になるはずです。
もちろんキーのまとまりを成立させるのがスケール内の音であり、あまりにそこから外れた音を使い過ぎるとそもそもキー自体があやふやなものになってしまうため注意が必要です。
さらには、スケール外の音をすんなりと聴けるようにするためにはコード進行の作り込みが必要になることも多いです。
使う頻度や使い方には気遣いが必要ですが、それでもこの「スケール外の音」が「ダサいメロディ」を回避するひとつのヒントとなるはずです。
2. メロディ:スケール内の音を跳躍させる
上記で挙げた「ドーレーミー」というメロディ例のように、スケール内の隣の音へ進めるように上下させる音の進め方を「順次進行」と呼びます。
順次進行はスムーズな音の変化を感じさせる一方、「ありきたり」という印象を与えることにもつながりやすいものとされています。
その回避策として考えられるのが「跳躍進行」で、これは、
スケール内の(隣の音の先にある)離れた音へ進ませるような音の進め方
を指すものです。
例えば、前述したメロディの例を
とアレンジするだけでも、「ド」から「ファ」、「ファ」から「シ」に向けて大きな音の跳躍が生まれ、ありきたりだという雰囲気は薄れます。
また、単に跳躍進行を盛り込めばいいというわけではなく、ある程度の親しみやすさにも配慮する必要があるため、適度な順次進行に跳躍進行を混ぜるのが最も理想的な形です。
個性的なメロディを考えるうえでは、このように「音の進め方」にも配慮することができます。
▼関連ページ
 「順次進行」「跳躍進行」の解説と、それらを活用したメロディ作りのアイディア
「順次進行」「跳躍進行」の解説と、それらを活用したメロディ作りのアイディア
3. メロディ:スケールの中心音を避ける
スケールの中で最も重要だとされるのは「中心音」で、それは例えば「Cメジャースケール」にある「ド」の音のことを指します。
中心音はそのキーにおける音使いのスタートでありゴールでもあるため、そこからメロディを始めたり、その音でメロディを終わらせたりすることで音の流れに安定感を持たせることができます。
前述した
などはその好例で、リスナーはこのようなメロディを聴くと
「中心音『ド』から始まる落ち着いたメロディ」
という印象を持ちます。
そのうえで、メロディに個性を出すためにこれを逆手に取り、あえて中心音を避けるように音を組み立てることが検討できます。
例えば、前述の例を
とするだけでも、単に「ド」から音をつなげた状態に比べて少しアレンジが加わったように感じられます。
上記は短いフレーズの例ですが、曲全体に広がるメロディの中で中心音の数をあえて減らし、音を落ち着かせないような状態に作り込むことが特徴的なメロディを作るためのアイディアとなるはずです。
4. メロディ:「スケール外の音」「跳躍進行」「中心音を避ける」の複合
上記で述べた点を複合させると、さらにメロディは個性のあるものになっていきます。
例えば、ここまでに例として挙げている「キー=Cメジャー」の曲において、
- 「中心音から始めない」
- 「スケール外の音を使う」
- 「離れた場所にある音への跳躍」
を複合させてメロディに取り入れると、
のようなメロディが考えられます。
これも短い例でありながら、前述した「ドーレーミー」というメロディに比べて、ここでテーマとしている「ダサい」が緩和されたメロディだと感じるはずです。
5. コード:ダイアトニックコード以外の活用
前述した「スケール外の音を活用する」というやり方をそのままコードに流用すると、
「ダイアトニックコード以外のコード(ノンダイアトニックコード)を活用する」
という方法につながります。
例えば「キー=Cメジャー」の曲において、ダイアトニックコードのみを使って
のようにコードをつなげるよりも、そこに「Caug」などのノンダイアトニックコードを挟み
とする方が、コードの響きには個性が生まれます。
このようなちょっとしたコードのアレンジが曲全体から感じられるサウンドの個性になり、それがいわゆる「ダサい」という印象をやわらげてくれます。
音楽理論を学習してコードアレンジの幅を広げる
これらを実施するためには、そもそも「どのようなノンダイアトニックコードが活用できるか」を把握しておく必要がありますが、それには「音楽理論」の学習が欠かせません。
理論を知るほどに活用できるノンダイアトニックコードの幅が広がっていくため、「ダサさ」を回避するためにもこのような知識の習得には積極的に取り組んでいくべきだといえるでしょう。
▼関連ページ
 ノンダイアトニックコード 意味とその種類の解説 活用のルールやコード進行例等
ノンダイアトニックコード 意味とその種類の解説 活用のルールやコード進行例等
 音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ
6. コード:セブンスコードやテンションコードを活用する
既にご紹介した「ダイアトニックコード」には、「C」や「Am」等の三つの構成音から成り立つ「三和音」状態のもの以外にも、音をそこからさらに増やした「セブンスコード」状態のものが存在します。
▼関連ページ
 セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について
セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について
コードの構成音が増えることでそこから感じられるサウンドは多彩になり、華やかさや大人っぽいムードがより強調されるため「ダサい」を回避する意味でこれらを活用することも検討できます。
また、そこからさらに音を増やした「テンションコード」の概念を取り入れることで、コード進行から生み出される雰囲気はジャズやR&Bに代表される都会的なものに近づいていきます。
あわせてそれらも、個性的なサウンドを作るために一役買ってれるはずです。
▼関連ページ
 テンションコード 概要とコード表記、コード進行例などの解説
テンションコード 概要とコード表記、コード進行例などの解説
7. リズム:単調なリズムを避ける
上記で例としてあげた
というメロディは、「ターターター」という単調なリズムを持っていますが、これをリズム的な観点から個性的なものにするためにはそこに複数の音符を複合させたり、休符を混ぜたりすることが検討できます。
以下は、単調なリズムを持つメロディの例です。

上記を実際に音として聴くと、これだけではやはり面白みのないメロディだという印象を持ってしまうはずです。
そのうえで、これを「音符の複合」や「休符」によってアレンジすると、以下のようになります。

ここではメロディの冒頭に8分休符を入れ、ところどころで4分音符と8分音符を混ぜたり、つなげたりしています。
アレンジ前のメロディとこちらを聴き比べることで、リズムを少し調節しただけでもそこから感じられる雰囲気に違いが生まれることがわかるはずです。
上記もシンプルな例ですが、このように音符の種類や休符の数に配慮したり、躍動感のあるリズムを生み出すようなアレンジができるとメロディはより聴き応えのあるものになっていきます。
▼関連ページ
 メロディのパターン・種類を考える|音階やリズムによる17のアイディア
メロディのパターン・種類を考える|音階やリズムによる17のアイディア
曲分析を通して「ダサくない」の基準を持つ
ここまでにご紹介したいくつかの手法はあくまでも例であり、「ダサい」の基準が人それぞれであるようにその原因もそれぞれに違うことから、
「こうすれば『ダサい』が改善される」
という明確な答えは出しづらいものだといえます。
結局のところそれを改善できるのは作った本人だけで、それには直接的な手法を覚えるよりも「曲作りの基準」を持ち、作曲の際の「判断力」を強化させることが大切です。
基準がないからダサくなる
作った曲を「ダサい曲(メロディ)だなあ」と感じるということは、少なからず自分の中に「ダサい・ダサくない」という基準を持てているということですが、では、
「『ダサくない曲』とは具体的にどのようなものなのか?」
と問われたら、多くの人はそれをぼんやりとしかイメージできないはずです。
裏を返すと、そのイメージをきちんと持ててさえいれば、必然的に理想とする曲に使づけていくことができるようになっていきます。
つまり、こちらのページでテーマとしている「ダサい」を乗り越えるためには、その「ダサくない曲」をきちんと定義として明らかにする必要があるのです。
「ダサい」を乗り越えるための「曲分析」の効能
これに最も効果があるのは
「曲を作曲的な視点から分析すること」
です。
自分が思う「良い曲」に作曲者の立場から向き合い、
- メロディ
- コード
- リズム
- 曲構成
などの観点から曲がどのように成り立っているかを紐解きます。
それを何曲も繰り返していくことで必然的にやるべきことが見えてきて、「ダサい」は改善されていきます。
▼関連ページ
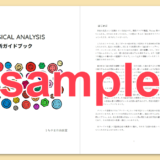 作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ
作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ
メロディ作りに強くなる本
メロディ作りのコツについて、「メロディ作りに強くなる本」というコンテンツとしてまとめています。 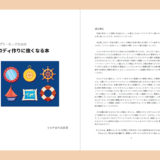 「メロディ作りに強くなる本」のご紹介
「メロディ作りに強くなる本」のご紹介
まとめ
作った曲を「ダサい」と感じてしまう状況を改善させるためのアイディアについてここまで考えてきましたが、つまるところその「ダサい」を乗り越えるために必要なのは「創作」と「振り返り」、そして曲分析を含む「作曲の勉強」です。
それは、
- 作曲をする
- その都度しっかりと一曲を作りきって、何ができて何ができなかったかを振り返る
- 音楽理論や作曲法の学習、曲分析の実施を通して「曲」に対する理解を深める
- また改めて作曲をする
という行動を循環させ、作曲のレベルを根本的に上げていくことを指します。
それによって必然的に「ダサい」と感じることは減り、徐々に自分の曲を認められるようになっていきます。
長い目で作曲と向き合い、好奇心を持って楽しみながらそれを乗り越えていってください。


 著者:
著者: